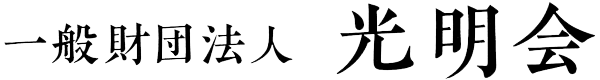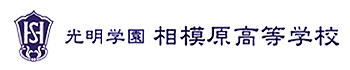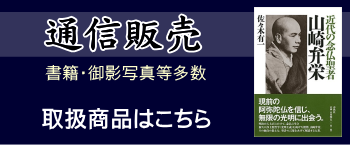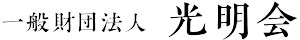一行三昧会
1月5日(日)に10名参加。午前中はお念仏、晨朝の礼拝、聖歌「諸根悦預讃」「感謝の歌」、午後は聖歌「念仏七覚支」、昏暮の礼拝をお称えしました。新しい年を迎えての初めての念仏会でもあり、茶話会では甘酒を楽しみました。
念仏と講話の会
1月19日(日)に13名参加。午前中はお念仏、晨朝の礼拝、聖歌。午後は、聖歌をお称えし、花輪講師のご講話を拝聴しました。
1月の講話のまとめ 花輪智之
効率主義・業績主義一辺倒の競争社会となり、多くの問題を抱える現代社会において自己の本来性を深く自覚しつつ、自他共に円満となる関係を築いていく道が求められている。
浄土教的宗教体験と真実なる世界観
華厳思想を高く評価した鈴木大拙は、第二次世界大戦直後に『霊性的日本の建設』を著し、本来の人間存在にとってあるべき社会の姿を、個々人が円成(仏性・仏心が円かに現成)しながら、お互いに他者を自己とし、他者のために働き合う社会として、その根本原理を華厳の事事無礙思想(一切の事物事象が相互に関係・融合し、そのままで真実の世界を完成する)に見出した。さらに、『仏教の大意』において、事事無礙法界を動かしている力は仏の大悲心であり、弥陀の誓願(大悲心)は華厳の法界を此土に現前せんとすることにあり、弥陀の大悲が分裂した個個事事の真珠が衆生の一々における浄土の荘厳であると表現し、知性的分別を超えて事事無礙となる霊性的直覚(無分別の分別)が実現していく原型を浄土教、殊に妙好人の言行の中に見出した。
河波上人は、論文『浄土教の宗教体験と世界観』において、「心仏衆生是三無差別」を説く『華厳経』の法界縁起の具体的展開は、念仏三昧の中で、弥陀の本願力の内容が衆生の一々における心の内容と働きになっていく場処(浄土)が開かれ、「心身土不二」となる浄土教的宗教体験に極まる事、知性的分別の自我(人と人、人と世界との隔たり)や捨此往彼の二世界観(神と人、神と世界との隔たり)にとらわれた現代の危機的状況の根源である、神、人、世界(自然)の和解不能な対立的関係を超克していく浄土教的宗教体験の意義を論じられた。そして、「西方遠しと謂う莫れ、唯十念に心を須いよ」(善導大師『往生礼讃』)を引用され、一念一念の念仏の実践が浄土教的世界観の展開に連なり、真実なる世界観を開いていく不可欠の契機となる事を強調された。
真実なる世界を開く「無対光」
河波上人は、『如来光明礼拝儀講座』において、弁栄聖者が明らかにされた十二光を讃え、殊に「如来光明の全体を尽くして無対光明のみ」として、弁栄聖者が説く「無対光」こそが、現代世界が当面する最大課題である神、人間、世界(自然)の三者の対立に対する根本解決であることを強調されている。
無対光の「心仏衆生是三無差別」かつ「心身土不二」の面を摂取門から仰ぎ見れば(如来光明礼拝儀「至心に勧請す」)、本より十界の一切を包む如来の真応身が在まさざる処なく、信愛の念に感応し、一人ひとりの心殿に大ミオヤの完全なるご分身(万徳の現われたる霊応身)を宿し、絶対的如来蔵性(一大霊性)およびその相好光明の妙色荘厳と一如である万徳円満の真応の内容を己が意とする全分度生の道(無住処涅槃、大ミオヤを絶対中心の一として、一切個々が相即相入円融無礙、弥陀即一切諸仏の諸仏(仏の子)となっていく宇宙解脱)を歩む身へと霊化して下さる。
「隣人愛」と「同体大悲の愛」
キリスト教の東方・西方教会の源底にあるテオーシス(神化)とテオリア(見神)の霊性は、単なる超然主義(二世界観)を超えて、神への脱自的愛(エロース)に伴い、聖霊によりもたらされる「神のみからだ」(人を神の子たらしめる神人性)を根拠とした神的生命(内なる神とその働き)の与かりと宇宙全一的交わり(エクレシア)への参与の道程およびその道程の中で神の愛(アガペー)と一体になる「隣人愛」の深まりに導いている。
一方、光明主義では超在一神的汎神である「無対光」の核心(一切に超絶し、一切に即せざるものなし)が、信愛の念に感応し霊応を発現する「如来のみからだ」(真応身)を根拠とした聖意体現かつ十界を我が身とした全分度生の活動を顕現する道程(念仏三十七道品)およびその道程における部分度生の活動(全分度生の部分現)の深まりを統一している。
超日月光(八正道)の境界で「自行」「化他」が完全円満に融合する全分度生を究竟とするとしても、五根五力、七覚支の各位での「化他」も部分度生として軽んじられるべきでない。また、「化他」を全きものとするために正しく「自行」を努めるべきであろう。
只一向、念弥陀三昧(常住不変である大悲の聖容を常に愛慕恋念する)の中で、大ミオヤの霊育におまかせ申し、段々と大ミオヤの無縁大悲(縁ぜざるものはない絶対無限の愛)に薫じられる「同体大悲の愛」をもって、「化他」を実現していくことが重要であろう。
「”つねに御顔を求めよ”と述べられる御方にむかって、愛の街道に出かけて行こう。」(アウグスティヌス)