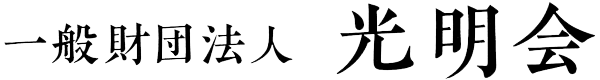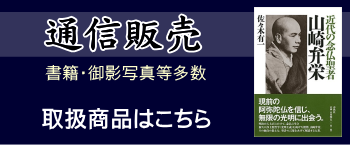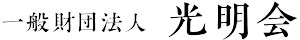関東支部報告
一行三昧の会
鎌尾美津江
◇日 時:2月5日(日)
◇会 場:光明園
◇講 話:佐々木有一氏
◇参加者:16名
寒気のなか光明園の白梅と濃淡の紅梅が共に咲き揃い、茶話会でも話題になりました。
日々のお念仏は刺繍の一刺一刺の如くであり、今はその織物を裏から見ている様でなかなか全体の模様を見渡せませんが、錦繍を成すひと針と信じ念じています。
〈ご講話〉 起行の用心 その6 五根五力(2)
田中木叉上人は信仰は根であり、念仏三昧は花である。人格が向上して霊格になるのが実である、と自分の為でなく人々の為に働く大乗仏教の根幹を教えておられます。
浄土への道しるべを富士山の登山に例えるならば、一歩踏み出すのが二種深信等であり、富士山まで歩み続けるのが五根五力です。まだまだ遠く時に雲がかかってその姿を見失ったりしますが(信・精進)、やがて雲がかかっていても富士山はあれだと確信できるようになり(念)、そして登り口まで近づき(定)、ついに登り口に立ちます(慧)。ここからは七覚支です。登り口では山の全貌は見えないけれども行く道がここだと確信でき(択法)とにかく歩を進め(精進)、そうしているうち足元に街中とは違う山肌を感じ(喜・軽安)いよいよ転換点とも言える八合目(定)、九合目(捨)、十合目(念)へと到達をめざします。この辺の、肉眼ではない心眼でみる心霊界は言葉では尽くせない神秘の領域でしょう。
- 五根五力
-
- ③念根、念力
- 次第にいつも如来様が念頭にかかっていて「憶念不忘」。(『佐々木為興上人遺文集』)
いよいよ信念を専らにするときは薫染、身に功成じて常に如来を恋念葵慕して忘れることあたわざるに至るを念根という。(『人生の帰趣』)
記憶としての心理状態にとどまって、まだ感情的執意的になって居らぬ故に、仏を念うの心理としては未だ完からず。(『無礙光』)
戒浄上人は唯識の心所では把住性が特色と説明されています。把住とはつかむ、その状態が続くということでしょう。 - ④定根、定力
- 次いである程度まで三昧に入ったところです。しかしまだまだ浅く、三昧に逍遥する程度と云われます。「三昧逍遥」。(『佐々木為興上人遺文集』)
一心に如来を念じて慈悲がその心念に薫染して久しければついに自己の心が如来心と成り、如来の心、自己の心となるごとくに感じられる、これを定根という。(『人生の帰趣』) - ⑤慧根、慧力
- 信の満位。心の曄?となり恩寵の喚起位に立ちいたります。「覚の自認」。(『佐々木為興上人遺文集』)
至心不断に念じて信念内に増長して如来の恩寵の和気に催され、信仰の曙光を見、心霊の曄?となる。これ喚起の満位とす。(『人生の帰趣』)
心所では簡択がキーワードで、簡択とは択び分けて疑いを断ずる働きです。
五根五力の目的は登り口に到達するまでの道のりで、本格的な登山の七覚支に入っていく為に欠かすことのできない条件(聖者のお言葉では前方便)です。そうして択法覚支で始まる七覚支で聖き心によみがえらせて頂くのです。
念仏と法話の会
志村念覚
◇日 時:2月19日(日)
◇会 場:光明園
◇法 話:大南龍昇園主
◇参加者:25名
光明園の紅梅や?梅の花が咲き匂い、二月の寒風の中にも春の兆しを感じました。午前中はお念仏と礼拝儀、午後は大南園主から「涅槃会に因んで」の題で、園主が長年取り組まれてきた仏教学の知見と弁栄聖者の教学についてわかりやすい御法話をいただきました。
〈御法話〉 涅槃会に因んで
- はじめに
- 涅槃会は二月十五日に入滅した釈尊の遺徳追慕と報恩のための法要である。前園主の河波定昌上人は昨年四月三日に遷化され、河波上人の九州大学の後輩であり光明園の責任役員や光明会関東支部長も歴任された田代直秀氏がその九ヶ月後の今年一月十日に逝去された。このお二人は信仰を共にする道友の印象であった。そのお二人を偲びながら、釈尊の二大弟子といわれた道友のサーリブッタ(舎利弗)とモッガラーナ(目連)を始めに取り上げ、第二に釈尊の臨終、第三に弁栄聖者の涅槃のみ教えについて見ていきたい。
- 一 舎利弗と目連
- 舎利弗は智慧第一、目連は神通第一といわれ、釈尊の十大弟子の中でも傑出した存在であった。この二人はマガダ国の同郷でバラモン階級に生まれ、年も同じで幼いころから仲がよく共に真実を求める心が強かった。この二大弟子の特長について、仏教学者の山辺習学は『仏弟子伝』(法蔵館出版)の中で、「サーリブッタ(舎利弗)を智慧の人とすれば、彼(目連)は意志の人であった。サーリブッタは智を与え、モッガラーナは行を与えた。サーリブッタを創業の人とすれば、彼は守成の人であった。前者は天の人、後者は地の人であった。この趣きは、経典の多くに記載されてある。」と記している。このように対称的な性格の二人であるが、舎利弗は釈尊の説法と宣布を支え、目連は釈尊の教団の諸問題を解決して教団運営を支える存在で、釈尊を中心とした三尊(釈迦如来の脇侍である文殊、普賢の両菩薩)の原型ともいわれる。この二人の優れた弟子は釈尊より年上であったためか師に先立って相次いで入滅し、釈尊は悲しみを深くしたことが初期経典の中に記されている。光明園を支えた河波上人と田代氏をこの二人の仏弟子に重ね偲びたい。
- 二 釈尊の臨終
- アーナンダ(阿難)もまた十大弟子のひとりである。釈尊に常に随って身の回りの世話をして支え、釈尊の言葉を一番多く聞いたということから多聞第一といわれる。釈尊の最後の旅はクシナガラの手前にある村での食膳に供された食べ合わせがわるかったせいか、釈尊はひどくお腹をこわし、クシナガラで涅槃の世界に入る。臨終の床の釈尊を悲しみ嘆く阿難に、釈尊は「やめよ、アーナンダよ。悲しむなかれ、嘆くなかれ。アーナンダよ。わたくしはかつてこのように説いたではないか、―すべての愛するもの・好むものからも別れ、離れ、異なる(生と死)に至るということを。およそ生じ(生)、存在し(住)、つくられ(異)、破壊さる(滅)べきものであるのに、それが破滅しないように、ということが、どうしてありえようか。アーナンダよ。そのようなことわりは存在しない。」と諭し、「アーナンダよ、長い間、お前は、慈愛ある、ためをはかる、安楽な、純一なる、無量の、身とことばとこころとの行為によって、向上し来れる人(=ゴータマ)に仕えてくれた。アーナンダよ、お前は善いことをしてくれた。努めはげむことを行え。速やかに汚れのないものとなるだろう。」と阿難を励まし教誡している。釈尊最後の言葉は、「すべては壊法(滅びてゆくもの)である。怠ることなく精進せよ。」であった。また、臨終の床にある釈尊にスバッダという遍歴遊行者が教えを請いに訪ねてきた。阿難は疲弊しきった釈尊を心配し、その願いを拒んだが、釈尊は阿難を呼び、スバッダを呼び寄せ、「スバッダよ。わたしは二十九歳で善を求めて出家した。スバッダよ。わたしは出家してから五十年余となった。正理と法の領域のみを歩んで来た。それ以外には《道の人》なるものも存在しない。」と釈尊の生涯のエッセンスとなるような言葉をスバッダに教誡し、スパッダは釈尊の最後の弟子となった。
中村元博士は『ゴータマ・ブッダ』において釈尊の臨終からも釈尊による思想的変革を見出すことができると主張し、「歴史的人物としてのゴータマはその臨終においてさえも、仏教というものを説かなかった。かれの説いたのは、いかなる思想家・宗教家でも歩むべき真実の道である。」と述べ、歩むべき真実の道とは苦からの解脱という人間の生き方そのものの希求だけに生涯をつくしたという。更に中村博士は「ところが後世の経典作者は右の詩に接続して、仏教という特殊な教えをつくってしまったのである。」と、釈尊はあくまで真実の道を追究したのであり、固定的な絶対的な教えの仏教という宗教をつくったのではないと説いている。弁栄聖者の光明主義も釈尊の教えを固定的、絶対的な教えとするのではなく、その主義とは普遍的な真理に至る道を説いたものなのである。 - 三 弁栄聖者の涅槃のみ教え
-
- ① 涅 槃
- 釈尊の臨終での阿難への教誡「努めはげむことを行なえ。速やかに汚れのないものとなるだろう。」という言葉は、弁栄聖者の涅槃の教え「仏教にて大法(大ミオヤの働き)に随って向上する終局を涅槃と云う。此の無上正覚(限りないめざめ)を得て涅槃に入るを目的とす。」(『人生の帰趣』一四二頁)に連なり、涅槃を死よりも生きていく目的とするものであると捉えている。この「向上する終局」について「仏教にて人生が自己最終の奥なる霊性の開発」とも説き、これはこの世に生存中に三身四智の仏眼、超日月光に於ける入の位の仏眼で明了に三昧体験する境地のことである。涅槃とはニルバーナを音写したもので、その字義は「吹き消すこと」「吹き消した状態」であり、すなわち煩悩の火を吹き消した状態を指すのが原義である。聖者は「霊性を開発」して「大霊(大ミオヤ)の目的なる大小両霊の合一(仏と人間の心との感応道交により一つになった状態)したる処即ち人類が生死の迷を超絶して絶対永遠生命に帰趣するを涅槃と云う。」と、生死の迷という煩悩をはなれるという本来の意味でも捉えている。
また、聖者は涅槃とはどのような場所であり、どのような世界であるかを「生死生滅を超えたる永遠常住の霊界、諸の聖者の安住する処を云う。涅槃に入りたる精神状態は常恒の平和と永遠の生命と一切の煩悩を寂滅したるただ幸福と光栄との光輝く処である。」とし、浄土教の極楽や法華経の寂光土、華厳経の蓮華蔵世界、無量寿界など言葉は違えども終局目的の帰趣する処である涅槃のことである。 - ② 有余涅槃と無余涅槃(無住処涅槃)
- 涅槃は死後に往くところか、または現世において入れるところかということについて、弁栄聖者は「釈尊以前の宗教には死後の極楽を以て永遠の目的とするけれども釈尊の発見なされた極楽は現世未来の別なくただ従来の精神生活の生死の凡夫であった精神が一変して無明の夢醒めて光明発見したる時がここを去らずして即ちここに於て涅槃光明界の精神に入る事が出来る。」(『人生の帰趣』一四二頁)と説き、肉体が有る涅槃ということで有余涅槃という。この肉体の中には肉の心も含まれるという。従って弁栄聖者の有余涅槃には、肉体を持ってこの世にいる時と、この世を去っているが肉の心を持っているため一時的に浄土にいる時の二つがある。慧眼、法眼、仏眼が開けても、三身四智の仏眼が得られなければ、滅後は肉体はないが如来化すべき肉の心が残っているために一時的暫定的に浄土に住する有余涅槃が実現する。そして如来のみ力で再び人間としてこの世に出て三身四智の仏眼を得るまで修行できるようにして下さる。(『光明主義玄義』六五、一〇四頁)
無余涅槃については「いよいよ肉体の命終り全く心霊の光明純粋なる常楽の心状態顕現するを無余涅槃と云う。」と、三身四智の仏眼を得た滅後の涅槃である。この三身四智の仏眼を得てからこの世を去ると、無余即無住処涅槃が実現する。無住処涅槃とは、「諸仏は生死に住せず、涅槃に住せず。常に神は常楽我浄の霊界に安住しながら一方には衆生済度の為に生死界に(分身応化し)現じて常恒に度生の功用を施し玉う。故に無住処涅槃とす。」(『光明の生活』三八四頁)と説くように、衆生済度のために身を分つダイナミックな涅槃である。この無住処涅槃は一般に大乗仏教では菩薩の涅槃をいうのであるが、弁栄聖者は諸仏の涅槃と説いている。
- おわりに
- 釈尊の教えは、真理に至る道の教えであり、どのような諸宗教や宗派でもこの道理を理解するならば仏教の実践となる。弁栄聖者の光明主義も同様に普遍的な真理に至る道であり、共に諸宗教を超越する教えといえよう。