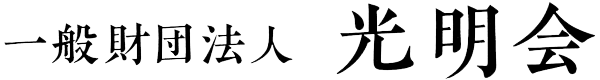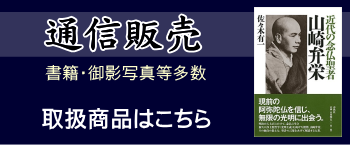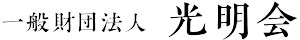機関誌ひかり2024年5月号掲載の「はじめての念仏」を、見本としてホームページ上に掲載させていただきます。合掌
願誉昭教
疑いからの念仏
前回、「疑いながらでも、稚拙な祈りであったとしても、とにかく声に南無阿弥陀仏と発して、仏さまとのご縁を結んでいただくことが最初歩」であるとお伝えいたしました。
日本で生活する私たちは、いったいどこで聞いたのか、またどこで覚えたのか、まったく知らないうちに「信じるものは救われる」というフレーズを聞き、なんとなく信仰というのは「信じなければならない」、「疑ってはいけない」と思い込んでいます。たしかに、信仰というくらいですから、疑うことなく、信じられていくべきです。ただし、信仰の道を、念仏の道を歩み始めようとする初歩者に、藪から棒に「阿弥陀仏は実在する、極楽はあるから、信じなさい、疑うな」という強要するようなお勧めは、まったく逆効果となることは間違いないでしょう。そのように言われた者の中には、ごく稀に「はい、信じます」という純真な方もいるかもしれませんが、普通は、「信じるなんて無理」と信仰の道を最初から拒否するか、もしくは途中で断念するかでしょう。
そのように強要されなくても、実際に念仏のスタートラインに立つ者(初歩者)にとって、阿弥陀仏や極楽の存在が「信じられない」というのは当然のことであり、圧倒的多数派といえます。そこで、今回はそのような「信じられない」という初歩者にお伝えしたい経文や念仏の先輩方の言葉を紹介していきたいと思うのです。正直、私自身この言葉に早く出会っておけば、十年以上も念仏の入口前で苦しまずに済んだのに、と思ってしまいます。ただ、苦しんだからこそ、その答えを探し求め、今皆さまにお伝えできるものと、このご縁を嬉しく思います。
◆『阿弥陀経』の説示
『阿弥陀経』の末尾に、
釈迦牟尼仏、能く甚難希有の事をなして、能く娑婆国土、五濁悪世の、劫濁・見濁・煩悩濁・衆生濁・命濁の中において、阿耨多羅三藐三菩提を得て、諸の衆生の為に、この一切世間、難信の法を説く
- 〈現代語訳〉
- 〔諸の仏さまがお釈迦さまを次のように讃えています。〕「お釈迦さまよ、〔あなたは〕この困難であり、極めて稀な事、〔つまり、阿弥陀仏や極楽についての教えの開示〕をよくぞ成し遂げて下さいました。この現実世界(娑婆)は五つの濁りに汚れた悪しき世の中です。〔その五つとは〕、時間の流れによる濁り(劫濁)・悪しき思想の濁り(見濁)・煩悩がはびこる濁り(煩悩濁)・人間の資質が劣化する濁り(衆生濁)・短命となる濁り(命濁)です。そのような〔現実世界〕の中で、〔お釈迦さまは〕悟りをお開きになり、その〔濁りの中で生活する〕生きとし生けるもの(衆生)のために、信じ難い〔極楽や念仏の〕教えを〔よくぞ〕説いて下さいました。
『阿弥陀経』というお経の内容は、阿弥陀仏の実在と極楽浄土の様子、そして念仏の修行によって往生できることを、お釈迦さまが舎利弗という弟子に語りかける形で、現在の私たちも含むすべての衆生に説き示して下さっています。そして、そのお経の最後に「よくぞ、その教えを伝えて下さった」と諸の仏さまがお釈迦さまを讃えておられるのです。
この『阿弥陀経』には、くり返し「信ずべし」と説かれています。ところが、このお経の最後に「難信の法」、つまり、「信じることが難しい教えである」と諸の仏さまがおっしゃっているのです。
そうすると、『阿弥陀経』の中で、「信ずべし(信じなさい)」と説きながら、最後に「難信の法(信じることは難しい)」というのは少し違和感を覚えます。ですが、そうでもないのです。
なぜなら、「信じ難い対象」(難信の法)だからこそ、「信じる」なのです。
例えば、私と友人が向かい合って対話しているとします。そのとき私が友人に「私がここにいることを信じて下さい」というのは変ですね。「信じるも何も、私の前にいるじゃない」となります。そう、確実なものを信じるというのは変なのです。なにか不確実な要素があるから「信じる」なのです。例えば、友人に眼を閉じてもらい、「私は絶対にあなたの前にいるから一分間、眼を開けないで信じて待ってて」。こういう状況であれば、「信じて」という言葉の使い方は妥当です。そのとき友人は、私との信頼関係ですんなり信じ、従ってくれたり、私のイタズラ好きを知っていて「何かたくらんでいるな」と疑ってみたり、いや何かお祝いのサプライズを企画してくれているみたいだから、ここは素直に眼を閉じてみようなど、様々な反応が想定されます。そのように、不確定な要素、言葉を換えれば、疑いの要素、未経験な要素、またさらに言葉を換えていうと、今は理解不能(難信の法)だけれども、その先にある何か、その何かを実感、体得してほしいから、「信ずべし」と説くのです。
◆『徒然草』の法然上人の言葉
つづいて、『徒然草』に伝えられている法然上人の御法語をみていきましょう。
或人、法然上人に、「念仏の時、睡にをかされて、行を怠り侍る事、いかがして、この障りを止め侍らん」と申しければ、「目の醒めたらんほど、念仏し給へ」と答へられたりける、いと尊かりけり。
また、「往生は一定と思へば一定、不定と思へば不定なり」と言はれけり。これも尊し。
また、「疑ひながらも念仏すれば、往生す」とも言はれけり。これもまた尊し。
(『徒然草』三十九段「或人、法然上人に」)
- 〈現代語訳〉
- ある人が法然上人に、「念仏をしている時、つい居眠りしてしまい行を怠ってしまいます。どうすればこの悪いくせを止められるのでしょうか。」と質問したら、上人は「目が覚めたら念仏しなさい」と答えられたそうだ。とても尊い導きである。
また、「極楽往生ということは、すでに決まっていると思うなら決まっているし、まだ決まっていないと思うなら決まっていないものです」と言われたそうだ。これも尊い導きである。
また、「疑いながらでも念仏をすれば極楽に往生します」と言われたそうだ。これも尊い導きである。
このように極めて優しい法然上人の言葉が伝えられています。まるで仏さまの視座から質問にお答えになっておられるような内容の言葉です。「眠ってしまってもいいよ。また、眼を覚ましたら念仏しましょう。疑ってしまってもいいよ。そんな弱き心の者でも、私(仏さま)が必ず育て・救い・導くよ、だから信頼してね」と。
普通の僧侶であれば、「眼を覚ませ」、「疑うな」と解答するのでしょう。ところが、法然上人の場合はそういう普通の解答ではなかった。だからこそ、『徒然草』の作者である吉田兼好は、そのような法然上人の導きを伝え聞き「尊し」と感嘆しているのでしょう。
ただし、ここに伝えられている「疑いながらも」というような言葉は、法然上人の他の文献から一切見つけることはできません。この『徒然草』の「疑いながら」という言葉の前に、「一定と思へば」と述べてあるように、やはりどこまでも、阿弥陀仏の存在や救いを、「間違いない」と疑わず信頼していくこと、それが信仰の本質でありますし、阿弥陀仏の救いの要件でもあるのです。救いの要件は二つ、「南無阿弥陀仏」と称えること、そして、疑いなく、信じ抜くこと。つまり、信仰の初歩においては、疑いながらの念仏ではあっても、そこに阿弥陀仏の光明のお育てをいただき、いずれ疑わず、信じられる安心決定の心境に至ることができる、ということなのです。
その安心決定の「疑わない」、「信じる」ということが救いの大切な大切な要件であるから、「疑いながらも」というような誤解を招く恐れのある言葉は、浄土宗の文献から伝承されていないのでしょう。ただし、法然上人のもとに救いを求めてやってくる者に対して、このように「疑いながらも、まず念仏してみなさい」との言葉を発せられていたであろうそのお姿は、法然上人の生涯と教えに接した者であれば容易に想像できます。
『徒然草』という浄土宗外の特殊な資料であったからこそ、その優しい法然上人の言葉が現代に伝えられているのかもしれません。
さて、ここの要点をまとめておきます。
念仏の最初歩はとにかく疑いながらであっても念仏を称えていきましょう。たとえ、そのような疑いながらの念仏であっても、その念仏を相続していく中で、仏さまの光明のお育てをいただき、いずれ信じる心(信仰心、安心)が確立されていきます。そして救い導かれていくのです。
◆頻出する「信じなさい」の言葉
経典や法然上人、弁栄上人、その他多くの念仏者の法語を拝読していくと、「信ずべし」、「疑いなく」、というような言葉が頻出します。それは、先に述べたように信仰の本質であり、また目指すべき、心の状態であるので当然といえます。ただ、そのような経典や法語を拝読していると、あまりにもその言葉が何度も何度も迫ってきますので、ここで多くの人が信仰的につまずくのです。
その「信ずべし」、「疑いなく」の現代語訳は、「信じなさい」、「信じるべきです」、「疑ってはいけません」などと記されています。もちろん正しい現代語訳です。ですが、初歩者にはとてもシンドイ言葉です。
「疑うな、信じろと言われても、疑ってしまいますし、どうしても信じられません。どうやら私には念仏の道は無理そうです」と。そんな信仰のつまずきをしてしまう方へ、もしくは、そんなつまずきをしないように、法然上人は「疑いながらも念仏すれば」と伝えられたのでしょう。したがって、最初に紹介した『阿弥陀経』の「信じるのが難しい教えです」との経文、そして「疑ってもいいよ」との法然上人の御法語をふまえ、初歩者は、頻出する「信ずべし」、「疑いなく」の言葉に接したとき、直訳した命令形としてではなく、優しく勧めて下さる言葉に変換して受け止めることをお勧めします。例えばこのように。
「最初は疑ってもいい。念仏する中でいずれ信じられるようになりますよ」と。
◆田中木叉上人の歌
明治時代、西洋から自然科学や哲学などの学問や思想が流入し、特に科学的な実証主義の考えが、優勢を極め、証明できないもの、また再現性のないものは怪しい、極楽なんて昔話であり、阿弥陀仏なんて幻覚だろう、という風潮に侵されていました。弁栄上人の後の世代、特に明治に青年時代を過ごした僧侶など、信仰的につまずく方が多くいました(残念ながら現代でも同様です)。弁栄上人の高弟の多くが、僧侶であるのにもかかわらず疑ってしまう、ということで深く心が苛まれ、苦悩しました。その一人が田中木叉上人(一八八四〜一九七四)です。木叉上人もその「疑い」により、念仏の行に入れず、学問的な方面のみの観念の遊戯に陥っていました。そんな苦しみ抜いた木叉上人だからこそ、その暗いトンネルから抜けだした体験を道詠に吐露して下さっています。木叉上人がそうであったように、念仏の入口前で行ずることなく、ただうろうろしてしまう初歩者の背中を優しく押してくれます。「先ず念仏よ」と。
ま心はおこりかねても唯となえ
称えて居ればおこるまごころ
称うれば声におじひの息かよう
み名よりひらく信心の華
(『光明歌集』三八~三九頁)
一つ目の歌は、仏さまを信頼する真心がなくても、ただ「南無阿弥陀仏」と称えてみましょう。称えていれば、必ずその真心は起こってきますよ、と。
二つ目の歌は、「南無阿弥陀仏」と称えていくならば、その声は(ただ念仏者の息のみならず、そこには)仏さまのお慈悲の声(息)が感応道交してくるのですよ。そして、その仏さまの御名である「南無阿弥陀仏」の声によって、信じるという心の華は開いていくのですよ、と。
この道詠は、木叉上人自身の信仰の道程を通して詠じられた実感の歌であると同時に、師である弁栄上人の教えを平易に伝える歌でもあります。
◆まとめ
今回は、疑いからの念仏でいい、そのような念仏であっても仏さまが導いてくださることを、経典や念仏者の言葉を通してお伝えしました。皆さまの念仏行の糧、また初歩者の行への呼び水となれば幸いです。
次回は木叉上人の道詠と同様のことを伝える弁栄上人の教えをお伝えしていくところから話を進めたいと思います。 合掌