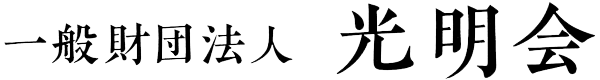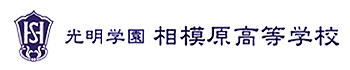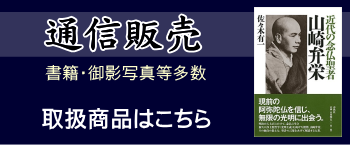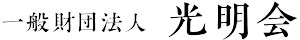「第四十九回 法のつどい」が5月24日(土)~25日(日)に、浄土宗総本山知恩院月光殿(京都市東山区)において開催されました。1都2府13県という全国から光友が集まり、延べ48名の参加者となりました。
開会式では、知恩院総務 執事の新谷上人、石原義堂代表理事よりご挨拶をいただき、念仏一会のあと小雨の中、弁栄上人の墓参を行い、お線香を手向けご供養をさせていただきました。
墓参を終え、爽やかな気持ちで念仏一会。そして、藤堂俊英師のご講話(後述)、記念撮影、夕食。その後、「暮の礼拝・念仏」に集中し、一日目は終わりましたが、多くの参加者との交流ともなる自由参加の座談会も開かれ、「お念仏の心がまえ」を先輩諸氏から伺う機会にもなりました。
二日目は、午前5時起床。知恩院様の阿弥陀堂にてお念仏、そして大殿にての晨朝法要への参加・晨朝法話の聴聞をさせていただき、清々しい一日のスタートとなりました。その後、朝食、清掃を行い、次は「朝の礼拝・念仏」に集中し、石原義堂師のご講話(後述)を拝聴しました。休憩後、聖歌「聖きみくに」の合唱を挟みながら光明会にご縁のあった上首上人・お上人の方々、多くの光友の皆様のご回向が行われました。昼食後は、川本剛空師のご講話(後述)を拝聴しました。
閉会式では、知恩院の新谷上人が柏崎の極楽寺様を地震のお見舞いの際に訪問され、その際の弁栄上人入滅の地を参拝されたご縁、百回忌の両国回向院での「福田行誡上人と山崎弁栄上人」の遺墨展を鑑賞されたご縁のお話がありました。最後に石原代表理事よりご挨拶があり、来年の50回「法のつどい」は、5月23日(土)、24日(日)知恩院様で開催される旨のお話しがありました。
二日間、司会、進行、維那等に労をとっていただきました、鶴山恒教上人、亀山政臣上人、石川乗願上人、鶴山豊教上人および光明会役員の皆様に御礼を申し上げます。
なお、個人的で恐縮ですが、光明学園相模原高等学校から校長先生をはじめとして8名のご参加をいただいたこと、また、前上首の河波定昌上人のお嬢さん、お孫さん、ひ孫となる双子の女児(3歳)の参加をいただいたことを嬉しく思いました。
来年は50回という記念となる「法のつどい」に、多くの光友の皆様が集うことを願って帰路につきました。
講話
藤堂俊英師 「人を育む言葉(声)の力〜法爾の道理としての~」
石原義堂師 「凡入報土(救我と度我)」
川本剛空師 「三十七道品序説」
講話の感想・まとめにつきましては、関東支部の花輪智之氏、田代泰彦氏にお願いしました。
藤堂俊英師のご法話「人を育む音声(声)の力」
花輪智之
- 【概要】
- 大乗仏教が説く世界の基盤である五大種(地・水・火・風・空)の言葉は私たちが住む世界や身体の説明に使われるだけではなく、浄土に往生している菩薩等に備わる徳の説明にも使われる。そのことは私たちが生命活動や浄土の住人にふさわしい徳を成立させるお手本に囲まれて暮らしている事を示唆している。弁栄聖者は、この世界も、行きつくところである御仏の御心にかなうようにと設けられた学び舎である事を示すため、次の歌をお作りになられた。
人の世もついのみむねにかなわしむ
この学屋としるやしらずや
浄土宗の三祖良忠上人は、「萬行の中に勝りたる事、念仏に過ぎたるはなし。…心に弥陀を思ひて、その心に勧められて、また口に唱ふ。念は声を勧め、声は念を起こす。常に弥陀を忘れず行ずるなり。…仏本願の心もこの故かと覚えて感涙押さへがたし。」と語られている。法然上人が名号をもって罪悪の衆生を導く弥陀の本願に”法爾(自然)の道理”という言葉を使われているように、南無阿弥陀仏という言葉(名号)には、私たちの心を御仏の御心に叶うように育む力が備わっている。そこを法然上人は万徳所帰の名号(智慧と慈悲のあらゆる徳が収まることば)と言われ、弁栄聖者は次のように歌われた。
萬徳の光の名号称へては
こころにみだのみむねみたさん
一向に佛をおもふこころこそ
佛の来たらんちかみちぞかし - 【所感】
- 浄土宗とともに光明主義を信仰の拠所とする人々に、心を注ぐのは、名号なのか、御姿なのか議論はあろうかと思いますが、聖歌『念仏七覚支』の冒頭の「弥陀の身色紫金にて円光徹照したまえる端正無比の相好を御名を通して念おえよ」の言葉を大事にしたいと思います。そこにこそ、『西宗要』の中で、三昧発得後の法然上人が二祖聖光上人に指南された念仏の心得、すなわち『般舟三昧経』から「わが名を念ぜよ」と、弥陀本願の意を得た善導大師の深意(心眼で活きた如来様に見える中で、如来の大悲召喚を実感したのであろう)が「阿弥陀仏の真金色の身。光明徹照し、端正無比にして、心眼の前にましますと想念せよ」(『観念法門』)の一文にあることを明らかにされた心念口称の意の相続があると思います。
弁栄聖者が「如来の内容(万徳そのものである相好光明)を知見せしむるは尤も大事のことなり」(『無辺光』)と言われたように、木叉上人は、その内容である相好光明を頂くことの大事を強調しつつ、次のように指南されています。
「御姿を通さずに如来様の光明を南無阿弥陀仏と称名で頂く。それでも悪くはありませんが、長く精神を集中、そこへ引っ付けておくということは、凡悪のわれわれにはできないのです。有形的でなければ、三時間、五時間はなかなか続かない。仏道修行をしてみると初めて分かるのです。いかに御姿が大事であるということが。恋しくなるのですよ。私どもの実験では、あの御姿が恋しくなるのです。恋しさ、懐かしさを宗教情操といいます。宗教情操が発達してこない間は、失礼ですけれども、私どもが体験することは本物ではないのです。」(木叉上人の晩年の講話より)
石原義堂師「凡入報土(救我と度我)」
田代泰彦
終始穏やかな語り口と、ご自身のことにはとても控えめなお姿が印象的なご法話でした。法然上人が如何に庶民農民の苦境に心を痛め、それを救う教えとして浄土宗を開いたことを、とてもわかり易く説明していただいたと思いました。
昨年、開宗から八五〇年を経た浄土宗について、万人救済こそ法然上人の御教えであり、凡入報土という精神であること。凡入報土とは、凡夫の報土であって、六道輪廻を繰り返す人間である凡夫が、阿弥陀如来様のお念仏によって報身阿弥陀如来様の住む世界へ一人も漏らさず、往生(帰趣)するという意味である。
法然上人がこのような御教えを開かれた背景として、幼くして父親を殺害されたこと。それは慎ましく暮らす農民への重い年貢が原因だった。若くして比叡山で頭角を現し将来を嘱望される身でありながら、黒谷での一切経から善導大師の御教えに深く感銘を受け、その教えを深く理解する遊蓮房円照との出会いにより、学問だけでなく実体験として阿弥陀如来の本願力を確信したこと。このような体験を積まれながら、いつも背後には飢饉に苦しむ農民や庶民の姿があった。今を生きる我々には想像もつかない、明日をも知れぬ人々に、仏様は南無阿弥陀仏とお唱えすれば、必ず迎えてお浄土の世界へ導いてくださると。この教えにどんなにか人々は救われたことであったか。
「御仏の無碍の光に会う人は漏らさず救う教えこそすれ」これを救我という。また、度我とは、自分がお念仏して立派にならなければ人を導くことができない。それには如来様の万徳というものをお念仏によって受けさせていただくというもの。そのためには、酬因感果の阿弥陀如来様ではなくして、法蔵菩薩の迹を垂れて私たちを導いて下さった本より宇宙に在り通しである真理そのもの、すなわち本有の真実の阿弥陀如来様をしっかりと念じていくことが必要です。その真実の如来様が、弁栄聖者が言われる超在一神的汎神である大ミオヤです。
本当に皆さんがお念仏を喜ぶようになってくださるには、どうか宇宙の真理である真実の阿弥陀如来様をこころからお慕いし、お念仏を励んでいただきたいと思います。
川本剛空師 「三十七道品序説」
花輪智之
- 【概要】
- 三十七道品は元々、小乗仏教で説かれたものであり、四諦説(苦諦と集諦は迷妄の世界の果と因、滅諦と道諦は証悟の世界の果と因)の道諦に相当する。大乗仏教でも『阿弥陀経』や道元禅師の著作等で言及されている。弁栄聖者は自らの三昧体験の内容を基に念仏三十七道品の行道を明らかにされたが、その行程は十二光大系を基にしなければ理解できない。
一、四念処は光化の心相(清浄光、歓喜光、智慧光、不断光)、二、四神足は三心の内容である信楽の愛の面、三、四正勤は無礙光、四、五根と、五、五力は難思光、六、七覚支は無称光、七、八正道は超日月光と関連しており、聖者においては、一〜五が道諦、六、七は道諦から滅諦への突入に相当するであろう。
特に四念処では御光に照らされて、現在的自己である自分の性について、清浄光により不浄、歓喜光により苦毒、不断光により無常、智慧光により無我(無明)の各面に気づかせて頂く。また、念仏三十七道品は七覚支が中心となるので、聖歌『念仏七覚支』の言葉に注視すること、念仏の対象が万徳にあるのをおさえることが大事である。 - 【所感】
- 念仏三十七道品の道諦、滅諦を仰信(大ミオヤの真理を一心一向に仰いで信じる)、証信(大ミオヤの実在本質を三昧体験の証明により信認する)で捉えるならば、道諦は大ミオヤの御光に照らされて五力までに信愛欲の三心が一体となった三味心が養われ(証信が始まる)、心の曄曈となる仰信の深まりに相当し、滅諦は親子相憶う親密なる関係の下、三昧心に大ミオヤの相好光明が融合して下さる(無称光)中での証信と仰信の円環的深まり、終局(超日月光)において大ミオヤと万徳の内容の面で親子一体かつ仏子として永遠の親子となり、証信と仰信とが完全円満に一体となることに相当するでしょう。
一向に佛をおもふこころこそ
佛の来たらんちかみちぞかし
の御歌のごとく、弁栄聖者は念仏三十七道品により、終局である証果(大ミオヤの万徳)が因位の一切衆生の各各を法爾の道理(親密なる因縁)により摂取せしめる超在一神的汎神にして本有無作の報身である大ミオヤ(大宇宙全一の一大人格)の無縁大悲(縁ぜざるものはない絶対無限の愛)にかなう念弥陀三昧の道(大ミオヤのお育てにおまかせ申し、見不見にかかわらず、只一向、本より一切各各の真正面に在しまして大悲のまなざしをもって見そなわし給う大ミオヤの万徳円満の聖容に、聖名を通し恭敬と愛慕の心を注ぐ)を御示しになられたのでしょう。
「南無と呼ぶ声にあみだは真(ま)に向ふ、おもひあぐればありがたきかな」(弁栄聖者)
以上、法のつどいの報告でした。合掌