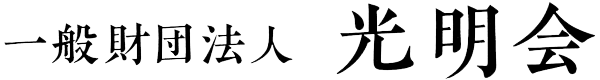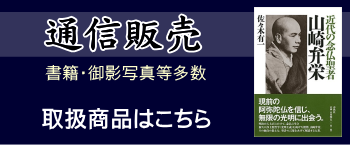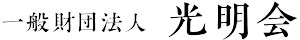乳房のひととせ 下巻39
中井常次郎(弁常居士)著
◇十 法然院(つづき)
日曜日には終日寺でお念仏をした。その時、供養された昼食から察するに、寺は随分粗食のようであった。あれで僧侶達の健康が保てるかと気の毒に思った。
十月二十一日、夜、毛布や衣類を担ぎ、傘や提灯をさげて金毛院へ泊りに行った。日中ならば、とても人目を憚る姿であった。
その後は毎夜、金毛院で泊り、朝晩お念仏を申しそこから学校へ通った。毎朝四時頃から起きて念仏した為、学校で居眠りが出て困る事も有った。
或日夕方、仕事を終えて家へ帰ろうとしていると、電気科の一学生が私の室を訪ね来て「私は人生に就いて色々考えてみますが、解決がつかず、あきらめてみても安心できず、僧侶達に聞いても満足を得ませんから、お教えを乞いに来ました」という。
それから二人は二時間ばかりも語り合った。別れる時、彼は「前途に光明を認めました」といって喜んだ。
とっぷり暮れた夕闇の中、家に帰り、夕食後、明日の準備をしておき、十町余りの淋しい野道を辿り、金毛院へ泊りに行った。
十一月の中頃となり、年末が近づき、家に女や子供を残して寺に泊るは物騒だという友の忠告を聞いた。如何にもそうだと自分の行き過ぎをとがめ、その後は宅から寺へ通った。妻も「近処の人達は、あなたがなぜ法然院へ泊りに行くのか不思議に思っているらしい、家庭に不和でも有るのかと思われはせぬかと心配しています」という。
十一月二十一日、日曜日。終日、金毛院でお念仏を申したり、「光明」誌の印刷をして過ごした。
この日、院主の兄上が金毛院で養生される事になったから、我々に引き上げてくれという仰せが有った。それ故、翌日、机や印刷機械を持ち帰り、金毛院とお別れした。忍徴上人は如何思召したやら。水は低きに流れてもその性を変えず、糞は金鉢に盛られても悪嗅を改めない。
弁栄上人は曾て「法然上人以来、徳本行者ほど内感豊かな念仏者は無い」と仰せられたそうであるが、徳本行者が上京の時は常に法然院で泊られたという事である。当時の院主、聖阿上人は行者の弟子であり、享和三年十月に行者は此処法然院で髪を剃り、化他の因縁が熟したとてその時より山居の姿を改められたゆかりの旧跡である。また、典寿律師という学者が金毛院で大小の経典を講ぜられしを聞き、行者は「律師の学解は、やや大菩薩の悟道に近い」と評された事なども有った。甚だ畏れ多い事ながら、著者は行者と同じ紀州の産たる光栄を思い、行者と深き因縁のこの法然院と金毛院は著者にもまた一層深き親しみを感ずる。
◇十一 両手
あるじ死にてその家衰え、子女の育ち宜しからざる例甚だ多し。諸の団体にもこの事あり。人おのおの垢質あり、我執を通さんとして争いを起す。
釈尊直下の教団においてさえ不和生じ、我執を固執して争いしという。
或る時、弟子達の間に些細な事より争い起こり、次第に拡大して二派に別れ、大いに争った。
世尊は彼等に向かい「争いをやめよ。不和を続けてはならぬ」と三度びまでも諭された。けれども彼等は仏の教誡を聞き入れなかった。
世尊は、為に長災王の昔話をして、「怨は怨を返す事によって鎮まらず、恕す事に依って鎮まる。恨は長く続けてはならぬ。友情は軽々しく捨ててはならぬ」と説き聞かせ、更に、「これは剣を執る王家が怨を恕す事に依って和合し、平和を獲た物語りである。汝等は出家ではないか、互に恕し、相和せよ」と懇ろに諭された。しかるに彼等は尚も争いを続けた。
世尊は独り静かに森に入り給い、やがてその地を去って、祗園精舎へ赴かれた。
土地の人達は世尊の去られしは、弟子等の争いに因ると知って彼等への供養を断った。彼等は初めて罪を知り、世尊の御許に到り懺悔し、和合を誓い、平和を取り返したという事である。
又、跋難陀比丘の如きは、世尊の入滅を聞いて悲しむ弟子達に向かい「汝等、嘆く勿れ、あの老人が生きていた間は、いつも我等を束縛した。我々をしかる事を常とした。今は気楽になったではないか」と悪口をいった。
大恩教主世尊の涅槃に当り、大衆悲嘆の最中に、斯かる毒舌を吐く比丘が仏の教団の中にありしを思えば、吾等光明会員の中にも不心得者の存在するはやむを得ぬ。
上人御在世の当時、我等も争った事がある。上人はそれを巧に丸められたお手ぎわ、道理とお慈悲の籠った裁き方、無作法者を改心させられた有難い教誡などを思い出して追慕の念を新たにすると共に、滅後の残党をして自警せしめ、教団の興隆を祈念する後の世の志士達の為に、事実の一端を記して参考に供しようと思う。羞を晒らすも後進の戒めとならば幸である。
(つづく)