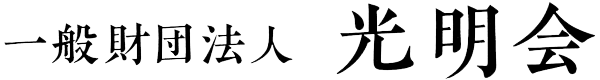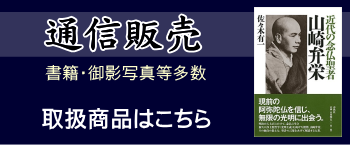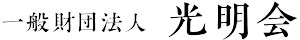乳房のひととせ 下巻41
中井常次郎(弁常居士)著
◇十二 十月の別時(つづき)
自分も信者の村を造りたいと思っていたから、氏は我が為には先輩であり、日向の新しい村は良い試験場であると思い、講演の後、氏と面談した。
新しい村の指導者として弁栄上人を紹介し、都合がつくならば、今からでも当麻山へ案内して上人に会ってほしいといった。けれども氏は明日大阪で、明後日は神戸で講演する約束であるから、ゆっくりしていられぬという事であった。それ故、他日を期して別れた。
その後、著者は和歌山へ帰り、温室に洋蘭を育てつつ念仏行をカモフラージュしていた頃、武者小路氏夫妻は暫く和歌浦に来て寓居を構えられた事がある。一日余の温室を訪ねられ、世間話を交したけれども、その時は既に弁栄上人遷化の後であり、氏もまた新しい村に対する熱が冷えていたようで有ったから、それに就いて語らなかった。
◇十三 聞き書き 其の十二
十月十六日~二十日 知恩院勢至堂別時会説教
(一)別時念仏の要領
二祖上人は宗祖に八ケ年つき添うた方であるが、別時念仏の心得に就いて「念仏には所求(目的)なかるべからず」と述べられてある。
ロウソクに火のつくのは暫らくであるけれども、火はロウソクの無くなるまで燃え続ける。人に信仰の火のつくのは暫らくの間であるが、その人一生涯光明生活となってこの世界で燃え、死後も永遠の光明として輝くのである。
動物生活のみならば、人生は闇である。如来の光明を受けるのが人生の目的である。心に如来の光明を燃えつかすのが念仏三昧の妙行である。十二月八日の暁方に如来の光明が釈尊のお心に燃えついたのである。元祖大師の心に燃えついた信仰の火は当時の人の心に燃え、今に輝いている。
月影の到らぬ里は無けれども
ながむる人の心にぞすむ
如来の光明はどこにでも照り輝いているけれども、外から見えない。信仰が燃えつくと見える。
○念仏三昧を宗となし、往生浄土を体となす。
一心に弥陀を念ずれば、自分と阿弥陀様とが一つになる。これを三昧という。暗と光明と合すれば明るくなる。
往生浄土に二つの意味がある。『大原談議』に往生に「かわる」という訓がある。即ち往生とは弥陀の光明中に生まれかわる事である。
生まれかわりに、心の生まれ更わりと身の生まれ変わりとある。お釈迦様の御在世中には、はっきり有余と無余の両涅槃が有った。涅槃とは弥陀の光明の実現した世界である。その光明生活に有余と無余との二種ある。有余涅槃とは肉体を持ちながら、教えの儘に修行せば、心は極楽の生活となる事であって「心ひろく、体ゆたかなり」といっている。心が暗いと世の中は狭い。信仰心が開けぬ間は人の心は狭い。この五尺の身体を心の住居だと思っている。
「往生浄土を体となす、」の「体」とは目的の事である。弥陀の光明を心に燃えつけるのが念仏三昧の目的である。
心の向け方を誤る時は、如何に努力しても信仰の火は燃えつかぬ。念仏三昧とは、一心に心を弥陀に向ける事である。ロウソクを燃え火の上に持ち行けば、すぐ火は燃えつくけれども、信仰の火は業障、罪障のために、なかなか燃えつき難い。常に働いている五欲の心が表にあるから、一時如来の光明を感じても、なかなか心に燃えつかぬ。人に辱められると怒りの炎は直ぐ心に燃えつく。
一切の衆生は悉く仏性を持っているけれども、仏性は煩悩に覆われて光明に触れない。業障、罪障、煩悩障という三障が除かれると光明を感ずるようになる。この障は自力では、なかなか除かれない。一心に念仏すれば炎王光に照らされて障りは除かれる。
業障――生まれながら持っている障
罪障――この世で造った罪の障
煩悩障――煩悩が有るから未来に罪を造り、そのために生ずる障りである。
聞けども聞こえず(説法を聞いても信ぜられぬ事)、見れども見えざるは(聖者を見ても聖者とは思わぬ)初めて三悪道から人間世界に生まれた人であると経に出ている。これらの人々は説法を聞いても信じようとはせぬ。
どうすれば自分の罪を知る事ができるか。弥陀の光明中にありながら、信仰の火が燃えつかぬは、業障の為である。念々称名、常懺悔と懺侮の涙を流して障りを除いて頂かねばならぬ。業障が薄らげば、光明を感ずるようになる。光明が心に燃えつけば、一生の間光明生活となる。即ちそれからの日暮らしは、極楽世界への旅となる。ロウソクは重さの無い火に食べられてしまうように、三悪道の罪も如来の光明に食べられてしまう。
(二)阿弥陀仏と心を西に空蝉の
もぬけ果てたる声ぞ涼しき
信心の水無き処に如来の光明は映らぬ。水月感応という事がある。信仰は澄める水の如く、如来の光明を反映する。念とは仏思の心である。この心が次第に深くなれば三昧に入る。
(つづく)