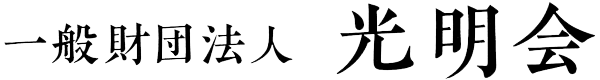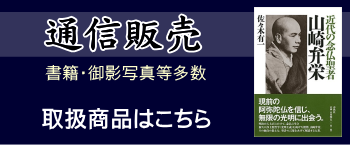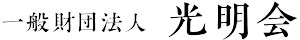乳房のひととせ 下巻42
中井常次郎(弁常居士)著
◇十三 聞き書き 其の十二〔つづき〕
十月十六日~二十日
知恩院勢至堂別時会説教
(三) 第十八願
元祖大師の心に信仰の花咲き実を結んだように、吾等の心にも同じ花咲き実は結ぶ。それは第十八願に依る。
信仰が進めば如来に対する愛楽心は深まり、感情的信仰となる。
願とは親が子に対する望みである。人が子に対する望みは、立派な世嗣ぎにしたいという事である。如来の願は衆生に親の如く円満なる徳を譲りたいという事である。四十八願のうち第十八願を除く外は、此の肉体生活が終って後、極楽で受ける有様を説いたものである。
○摂法身願――寿命無量、光明無量等一切諸仏が賞め称える徳を吾等に下さる。
○摂衆生願――浄土に生まれて天眼、天耳、他心、宿命、神足、漏尽等の六神通を得、悉皆金色の霊体を下さる事、即ち不完全なる肉体を無碍自在なる霊体に取替えて下さる願である。
私共が前世で犬であったとせば、死ぬ時、犬の五官を土に返し、今、人間として生まれ、新たに人間の五官を与えられたのである。そのように、今この身が死ねば、今度は本願により、浄土に生まれる時、六神通が与えられる。
○摂国土願――犬であった時には、家も衣も食器も持たなかった。人間に生まれると、道具、財産ができる。今度、浄土に生まれると、徳を積めば、いくらでも美しい衣が、金が無くとも身に具わる。洗濯の必要なき衣が心に着せられる。かくの如く総ての物は死と共に取替えられるけれども、変らぬものは心である。
心に二種ある。この世に出てから覚えた心は、死ぬ時に皆土に返す。経に「庫中の財は、死ぬ時、置き去る」と。霊魂は取替えられぬ。(仏教では、霊魂といわぬが、今は仮にこの名称を借る。)
第十八願は、人がこの世で生きている間に、浄土へ生まれる為に実を熟させる方法を教えたものである。
修行の結果はアラヤ識という霊魂に実が結ぶ。人が死ねば、再び人間として生まれる事は少ない。多くは三悪道に堕ちる。念仏の種を心田地に蒔けば、五根という信心の根が出る。それから信心開けて仏を見る。下品下生の人は臨終に蓮台を見て往生する。十二大劫の間、花開かぬ。
至心信楽の至心は至誠である。真実心である。これは心の土台である。誠とは偽らぬ心である。誠は形式であり容器である。如来の慈悲という内容を盛る容器が誠である。真実心という容器に入れる内容物は信と楽と欲とである。うそをいわぬばかりの誠はなかみが無い。人に負けないように、一時励むとも、相手が無くなれば怠り、退歩するは、真実心が無いからである。
(四)阿弥陀仏というより外は津の国の浪速のことは悪しかりぬべし(法然上人)
元祖大師〔法然上人〕は十八歳にして既に天台の三大部を解する知識をお持ちになっていた。天台の三大部が解かれれば、一切経の心が読めたといって良い程、大切なものである。それ故、大師は十八歳の時、一切経を理解する学識を持っていたのである。
その後一切経を五度繰り返して読まれた。また、唐から伝わった仏書を皆見られた。
大師は釈尊一代の間に説かれた仏教の中、何れの道から入れば最も易く信仰に入り得るかと心配なされた。当時、宋に有る位の本や宗派は皆、日本にも有る事を宗祖は知っていたから、あちらへ渡って調べる必要を認めなかったのである。
かかる事情のもとに、大師は一代仏教より選択して開かれたのが念仏宗である。その選択の標準は勝易の二点であった。即ち念仏は法として勝れ、王位を占め、行として易く、時所所縁を選ばぬ二利を兼ね備えている。法が如何に勝れても、行が難しければ、法の功徳を受け難い。また、行が易くとも、法にねうち無くば修行する価値が無い。
阿弥陀仏は万法中に念仏を選びて我が名を呼べと仰せられた。釈迦もまた、同じ事を仰せられた。
念仏は何故、法において最も勝れているかといえば、念仏の一行に万行を蔵め、名体不離の故である。阿弥陀仏という御名の中には三身、四智、十力、四無畏、十八不具法等のあらゆる徳が含まれている。家といえば棟も瓦も、柱も一切が含まれているように、名号の中には如来の万徳が含まれている。
口も心も名号と一致せねばならぬ。仏の名号を称えると、何とお答えがあるか。どう聞こえるか。如来が「わが名を呼べ」と仰せられるから、御名を呼んだのに、お答えなきは、心がよそへ行くからである。選ばれた者にはお答えがある。そのお答えは、肉の耳には聞こえぬけれども心に響く。
〔中国、儒教の経典の一つである〕『大学』に「心ここにあらざれば、見れども見えず、聞けども聞えず」とある。声を聞かんとすれば、千年待っても聞こえぬ。至心に念仏すれば、慈悲のお答えがある。有難い涙となって聞こえる。一心に念仏すれば、一々お答えがあるけれども、五蓋といって、五つの邪魔物があって三昧の障りをする。(五蓋とは貪、瞋、睡眠、疑、掉悔の五つである。)〔掉悔とは、心が昂ぶり頭に血が上った状態の掉挙と、心を悩ませる後悔のこと〕
(つづく)