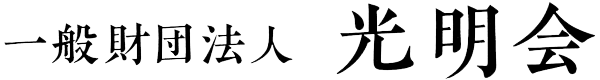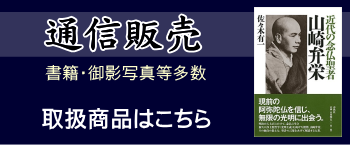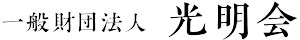乳房のひととせ 下巻43
中井常次郎(弁常居士)著
◇十三 聞き書き 其の十二〔つづき〕
十月十六日~二十日
知恩院勢至堂別時会説教
(十二)至心信楽欲生我国
念仏すれば信仰が進み、心は激しく働くようになる。愛と敬と調和すれば正しい信仰となる。初めは子が親を慕うように如来を愛する。次に夫婦の愛の如くになる。
如来を信ずる故に、仏種が蒔かれる。一心に念仏して真の信仰を得れば、身は凡夫なれど心は尊い。
信仰の初めには、如来を大み親なりと聞くも、他人の親のように思われたが、次第に情が深くなり、自分の親のように感じて来る。
人間の欲望の中心は死にたく無いという事である。けれども肉の永生はできない。それ故、霊的に活きねばならぬ。
人の心に異熟性あって、善悪何れにも変化する。三悪道は非人格、三善道は人格、四聖は霊格である。凡夫は欲で働く。
(十三) 極楽へつとめて早く出で立たば 身の終りには参り着きなむ(法然上人)
信仰生活の人は一日一日、極楽へ近づく。
凡夫の魂をアラヤ識という。アラヤ識で宇宙を見れば、どこまで行っても娑婆である。仏智を以て見れば、どこも極楽である。
三種の愛心――一、境界愛。二、自体愛。三、当生愛。境界愛の起る時は、まだ目が見え耳が聞こえる。自体愛の起る時は、目は見えず、耳は聞こえぬ。当生愛の起る時は、生まれる先の事が見えて、外の物は何も見えぬ。馬に生まれる者は、馬の交尾の有様のみを見る。それに見とれて馬の胎中に宿る。馬が慕わしくなって馬に生まれる。人間として生まれる者は、夫婦の交りを見て人間が慕わしくなる。その心に引かれて人の胎内に宿る。
中有は死んで後、まだ生まれぬ間の身である。中有の身は、まばたきの間に、遠くへ行く。非業を遂げた者は、多く中有となって迷う。中有の命は三、四日のもの、十日一月、百年も迷っている者がある。
如来の慈悲の火の燃えつく処は、人の煩悩の外に無い。犬や猫の心に如来の慈悲の光は燃えつかぬ。念仏する目的は如来の光明を我が心に燃えつかす事である。如来の慈悲の火が、一人の人の心に燃えつけば、その人と交る人の暗い心にお慈悲が燃え移る。
私共が呼吸する時、清き酸素が忽ち炭酸ガスになるように、念仏すれば仏は即座に我が心に入り給えどすぐ煩悩となる。それ故、常に念仏せねばならぬ。
人は己が心を苦しめている間は、如来を忘れている。心苦しいのは、煩悩の悪いガスが溜っているからである。
◇十四 柏崎
(一) 最后の別時
十一月十六日より五日間、柏崎の極楽寺で弁栄上人御指導の別時があった。弟の平三郎も、それに参加した。彼は「三身の聖歌」の譜を作り、上人様に聞いて頂く心組であった。しかるに上人は御病気の為床に就かれ、佐々木和尚が導師代わりを勤めた事とて、彼は作曲の発表を見合わせた。今は「応身の讃」に対する音譜だけ残っているけれども、「法身と報身の讃」の譜は忘れられてしまった。
二十一日の早朝、弟は柏崎から京都へ帰って来た。そして上人が御病気だというから、自分は早速、見舞状を出した。
(二)柏崎へ
恒村さんは二十三日の夜行で柏崎へ立った。多くの患者を受持つ医師として、患者を置き去り、上人をお見舞い申した事は、上人思いの熱情からであったに違いない。多くの患者の臨終の席で、蕩々と大説法をする先生が、吾が子、幼きスミちゃんの死に当り、茄でた菜っ葉の如くに、顔色青ざめ萎れて、悔みの言葉を受けられたと同じ身内思いの感情が、上人の御身の上に注がれたものと思われる。
二十六日に恒村夫人から、電話で「上人は御重態である。午後の汽車で柏崎へ行こうと思う」と知らされた。自分はすぐ帰宅し、妻に電話の趣きを伝えた処、自分にも御見舞いに行くようにと勧められた。それで急ぎ旅装を調え、京都駅へ駆けつけた。午後二時十分発の汽車で恒村夫人と同道した。
二十七日の暁方、柏崎が近づいた頃、隣の車に佐々木和尚が乗っているのを知った。上人に代って高岡とかの別時へ導師に行って来たのだという事であった。柏崎の駅に着けば恒村、谷の両氏が夫人を迎えに来ていた。
極楽寺に着くや否や、自分は御病床に伺うと、上人は御褥からお手を出され、「ここへ、ここへ」と仰せられ、お十念を授けて下さった。「御病気は如何ですか」と申し上げようとすると「奥様の御病は如何ですか。共に新生涯に入るのですから」と、先ずこちらの事をお尋ね下されて恐縮した。
「共に新生涯に入る」と仰せられたのは、どういう意味であったか今に解からぬ。近い内に共に死ぬのだと予言されたのかと思ったが、妻は今に健在であるから、近き死の予言ではなく、たとい肉体が死んでも、心は共に光明中である、無余涅槃の新生涯に入るのだぞ、とお慰め下さったのかとも思った。
(つづく)