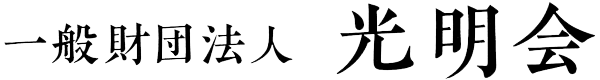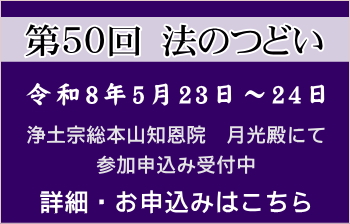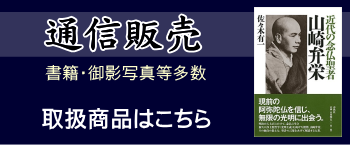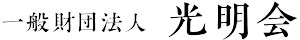乳房のひととせ 下巻32
中井常次郎(弁常居士)著
◇8 聞き書き 其の十(つづき)
当麻山無量光寺にて
八月四日よりの十二光仏講義
無間修―信仰の相続において、念々相続は上、時々相続は中、日々相続は下である。
己が過ちを知らば、すぐ懺悔せよ。そうせぬ時は、悪いくせが深く心に浸み込む故に、念々に懺悔せよ。
積極的には如来に向かって念々に進み、消極的には己が汚れを去るは無間修である。
長時修―以上三つの修行を生涯続けるのが長時修である。資料位で念仏三昧の準備をしておき、次の一週間で必ず発得できるという信念を得て別時に臨む。これが加行位である。しかる時は、一週間の後に見道位に進み、如来の光明を見る事ができる。今までは煩悩で行動していたが、見道位に入れば、無漏の聖道に入り初めたのである。かくなれば信仰が開発され、心の花が開いたのである。五根五力は準備時代であり、見道位に入って七覚支の花が開く。
七覚支(択法覚支、精進覚支、喜覚支、軽安覚支、定覚支、捨覚支、念覚支)
宗教的神秘の霊感を経験すれば、それだけ信仰の上に覚えができる。
- 択法覚支
- 択法とは簡択の意である。今までの修行により、信仰のめあてが定まった事である。即ち念仏するのは何の為かという見定めのついた事である。如来に向かって打ち込む心の的の定まった状態を択法覚支という。
- 精進覚支
- 一心にして余念なき状態である。大いに努力しなければ雑念に捕らわれる。
- 喜覚支
- 念仏三昧により、心が研けると夜明けの気分を感じ、三昧中に喜びを感ずる。
- 軽安覚支
- 喜びを通り越すと、軽安を覚える。外道は定中に喜楽捨を感じ、そこで止まり、それ以上進まぬ。三昧楽に味着してはいけない。
- 定覚支
- 定に入り、心は如来に融け込む。
- 捨覚支
- 初めは注意を怠ると、心は仏念いを離れるけれども、ここに到れば、任運無為に定に入る。何事も心を用いる間は苦しいものであるが、熟達すれば楽になり、興味が湧いて来る。定が自由になれば捨になる。
- 念覚支
- 捨が進めば念となる。即ち如来の中の自分である。加来と一体。自分の中に如来ましますようになる。この心から出る念と、今までの念とは全く異なる。
念は種子核を養う。念仏三昧により七覚支の花開き、身口意の三業に信仰が現れ、仏子の人格が成るのである。
三昧中の喜びや定中の感じは、口でいい表す事ができないから無称光という。
信仰とは如来の恩寵を仰いで、光明を獲得する事である。動植物を通じて生活に入れば、その持てる性質が発達する。米が俵の中にある間は、生理的変化を見せぬけれども、水田に蒔けば生活期に入り、芽生えて大きくなる。やがて花開き実を結ぶ。実を結べば、稲に肥を施しても大きくならぬ。信仰生活も、これとよく似ている。誰もが仏性を持って生まれて来ているが、放任して置いては俵の中の米の如く、仏子の性格が現れない。念仏して如来の光明に育てられる時は、水田の苗の如く、信仰は念々に育ち、花咲き、仏子としての人格が心の上に実るのである。肉体は心を実らすために必要である。
凡夫は小我を我として生死界にあり、二乗は小我を滅して真空真如を証得し、菩薩は真空真如を証得した上に如来心を己が心として活動する。
超日月光 体現位
地球上に在る一切の生物は太陽によって養われている如く、われらの心霊は如来の光明を離れては活きられぬ。如来の光明は太陽の光の到らぬ、人の心の奥まで照らす故に超日月光という。
- 如来の光明
- 智慧 六百巻の大般若はこの光より出る。
慈悲
威神 悪人を善人となす。霊化する。
日光(光線、熱線、化学線)
信仰は体現位に到れば、三業四威儀に如来心が現れる。三業とは身(行為)と口(言葉)と意(思想)とである。四威儀とは行、住、坐、臥をいう。
我等は動植物と等しく太陽に生かされているが、如来の光明を蒙り、霊に活かされ得るのは人間ばかりである。霊的光明の反射は弘法、法然、日蓮等の上に見る事ができる。如来の光明を受けた人と受けざる人との間に霊的に非常な差がある。
宗教の大事は人格の完成にある。人生を自覚せぬ人の日暮らしは動物生活である。
自覚しかけたのが信仰の喚起位で、心の花の開くは開発位、実を結ぶは体現位である。
如来の光明に育てられると、誠に麗しき内容ができる。人の性、相近く、習い相遠し。
三心…信・愛・欲
執心…愛と欲(悪に向けず、善に向け、執心して実を結ばしめよ)
『阿弥陀経』に「執持名号」とある。如何なる場合にも名号を執持して、仏子の実を結ばしめよ、との教えである。
真理を知る智慧を般若という。経を知る智慧である。経文に実相般若、観照般若、文字般若の三つある。『阿弥陀経』の実相般若は仏眼なき者には見えない。実相を仏眼で見るのが観照である。凡夫は実相を見る事ができないから、文字で示された経即ち文字般若を見る。毎朝の読経は生活の序文であり、一日の活動は本文である。
〈つづく〉