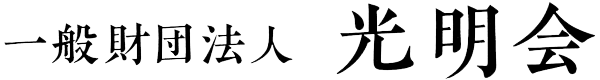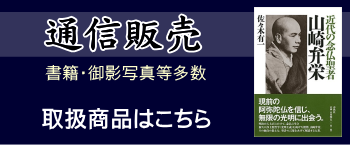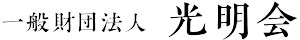乳房のひととせ 下巻36
中井常次郎(弁常居士)著
◇九 聞き書き 其の十一(つづき)
大正九年八月十八日~二十四日信州唐沢山阿弥陀寺別時説教
念仏に三通りの心がある。請求、感謝、咨嗟。
請求の念仏――請求とは如来に対する要求である。これに低きものと高きものとある。浄土宗で行われている「助け給え」という念仏は一生の間頼む意である。如来がどこで助けて下さるのか、いつ助けて下さるのかはっきりしておらぬ。我々はこの儘では地獄へ堕ちる外無いのであるが、如来のお慈悲で助けられる。有難い事であると感謝ばかりしているのが真宗である。助かった上は、もう助け給えというに及ばぬ事になる。請求の念仏とはかかる意ではない。初めは救われる為であるが、救われた後は霊の糧を求めるのである。初めは乳の要求であるが、進んでは味よき物を要求する。
我等は如来より心の衣食住を与えられる。信仰ができても捨て置けば退歩する。信仰が健全ならば念仏を要求する事が多くなる。活動中は閑居の時よりも多量の空気が要求されるように、活動的信仰には多くの念仏が必要である。
感謝の念仏――これは如来の大恩を思うて御名を称える念仏である。
咨嗟の念仏――何ともいうにいわれぬ広大なる如来の恩徳を感じた時の念仏である。
念仏中、霊感を得て声の出ぬ事がある。この時は咨嗟の念仏になる。悲しみ極まる時、言葉で説明せずに泣く。感謝の極は言葉にならぬ声になる。真宗の和讃の間に称える、あの長く引っ張る念仏は、お浄土の菩薩方が如来の威徳に感じ入って称える咨嗟の念仏をかたどったものである。
子供が一日よく遊べば親は喜ぶ。青年に成って一日遊び暮らせば親は心配する。宗教も法然上人や親鸞上人の〔活躍した〕時代は感謝の念仏でよかった。今日の宗教は救我で満足できない。度我を要求する。幸福だけでは満足できない。人格の完成を要求する。仏道修行の為には娑婆の一日一夜の生活は極楽の百年に優るという。今はここより外に良い道場は無い。ただ救われたいばかりならば、救われた上はいつまでも肉体上の不自由が失せぬこの世界で長居するは無意味である。作仏を目的とするならば一日も永く此の土に留まって修行するが良い。
お釈迦さまは人間の精神を改造する為に出て来られたのである。度我は努力主義である。ただしそれは如来の光明が加わっての努力である。人生は努力する処に価値がある。念仏中の心持ちで平生仕事せよ。
燃え続いて消えぬ念仏が念仏三昧である。念仏三昧に依って燃えついた如来の光明は永久に消えない。
思う心と思わるる心とが一つにならねば大慈悲の力もどうする事もできない。信仰が進めば自分が如来の慈悲に救われたように、人をも救いたくなる。親の手助けができるようになる。如来に対する敬愛の情は信仰の進むに連れて増す。敬により距りが生じ、愛により引きつけられる。愛の始めは肉的であって動物性に満足を与える。霊性より出た愛は美しくして内容は豊かである。
子を愛するは親の慈悲に同化さす為である。卑きものを愛すれば人格が卑くなる。
信より来る念仏は益々澄み、愛より来る念仏は益々篤くなり、念々に愛は増す。
(五)信仰生活
宗乗を知るばかりでは信仰心が生まれない。如来の実在を信じ、今現にここに在すと思い、一心に念仏すればやがて信根生じ、愛の信仰が芽生える。
愛に三位あり。母子的愛。異性的愛。夫婦的愛。
母子的愛――初めは子が母を慕うが如くに如来を愛慕する。人間相互の愛慕は生理的の自然である。如来と衆生との間にもこれと同様の関係がある。この愛は次第に発達する。
吾等が本来の親は如来であるが、肉の里親の方になついている。里親ができない事や聞いてくれない事を本来の親は容れて下さる。一心に念仏すれば慈悲のお育てを蒙り、如来に対して愛と親しみとを感ずるようになる。善導大師は衆生と仏の間には親縁、近縁、増上縁という三縁ありと申された。生みの親に告げられぬ事でも霊の親には何の憚りも無く告げられる。一心に如来を念ずれば耳に聞えぬけれども、心に答えて下さる。
異性的愛――『法華経』に「一心に仏を見んと欲して、身命を惜まずば、仏、現前して法を説き給う」と。タゴールは『暗室の王』という小説を書いて「自分(衆生)は王(如来)と結婚しているが、暗室の王なればまだ一度も夫の顔を見た事がない。或人はいう「王は美男子だ」と。又或人はいう「王は恐ろしい顔の人だ」と。常に王に仕える人(三昧発得の聖者)あり。その人に王の姿を問えば「あなたは自分で見なさい。私が有るがままに話しても疑うでしょう」と答えた。また、なぜ王に仕えるかの問いに答えて「吾が父は王のとりことなった。父の敵に仕えるのはなぜか、と聞かれてもわけが解らぬ」と。
これは全く事実を告げたものである。子供や親が死の王に捕われ、それが縁となって信仰に入り、如来に仕えるようになる事を示したものである。逆縁の恩寵により信仰に入る人が多い。なぜこの人が逆縁により信仰に入ったかわけが解らぬ。その事実を物語ったのが『暗室の王』である。(つづく)