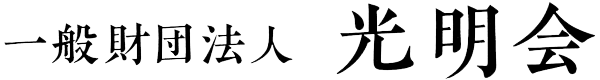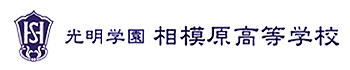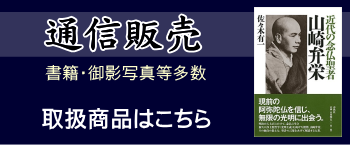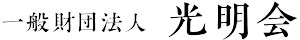山本 サチ子
小説家、藤沢周平の作品に出会ったのは三十代半ばの頃だった。光明園園主の河波昌先生の奥様から勧められたのです。奥様のご両親は山形県出身であり藤沢周平が両親と同じ山形県出身である理由からでした。この頃、私は子育てと仕事でまったく余裕がなかったこともあり、何年ものあいだ読むことができませんでした。
数年後、まず短編小説から入ろうと「玄鳥」から読み始めました。
面白くて気がつけば彼の小説の虜になり、短編、長編小説、どれもみな甲乙つけがたい作品ばかりであり、大きく心を揺さぶられました。
この時代小説は現在の山形県鶴岡市が舞台となっています。「玄鳥」、「三月の鮠」、「闇討ち」、「鷦鷯」、「浦島」等の短編は哀愁とユーモアがあります。どの作品も甲乙つけがたく、ここでは「玄鳥」と「鷦鷯」の二つの短編を取り上げて紹介します。
玄鳥
武士の生き方や信念をテーマにした小説である「士道もの」の作品、「玄鳥」は特に味わい深い。不幸な結婚とまでは言い難いが主人公の末次路の夫は少し冷淡な所がある。路は粗忽者だが夫よりはるかに人間らしい父の弟子、曽根兵六に寄せる思いが読む者の胸を打ちます。
「つばめが巣づくりをはじめたと、杢平(=家の下働き)がもうしております。いかがいたしましょうか」路は夫の背に回って裃を着せながら軽い調子で話しかけた。
「つばめ?」夫は前を向いたままで問い返した。長身だが肉の薄い背である。
「あれは追い払ったはずではないか」
「また戻って来たそうです」
「場所は同じところか」
「はい。門の軒下です」
「巣は壊せ」
夫はにべもなく言った。
「杢平が戻ったら、捨てさせろ」
この短い会話の中にも夫の冷淡な人格が伝わってきます。
ある秋、路と妹の節が庭隅で柿の実を取るのに苦心していました。丁度道場を訪れた兵六は、「それがしが捥いで進ぜましょう」と言い、柿の実を取ったが枝が折れて、したたか尻を打ち姉妹の介抱を受けた。
また、あるときは玄関と門の間の水たまりを飛び越えた際、泥に足をとられて三尺(約90センチ)も、すべり尻餅をついた。
路は笑いを噛み殺すのに苦労する。
路は後にも先にもあんなに笑ったことはない、と思い出を懐かしく振り返りました。
あるとき兵六は藩から追われることとなりました。
藩内に抗を起こした男がいた。その男は失脚した側の派閥の怨嗟の的になり、江戸から刺客が放たれた。そのときの警護人が曽根兵六であった。警護に失敗した兵六は藩から逆に刺客を放たれたのです。
主人公の路は、かつて父の弟子の曽根兵六が絶体絶命になったときに伝えるようにと亡き父からの口伝を伝授する。「風籟の型」である。はたして兵六が無事逃げ延びられたかは小説では描かれていない。
路は不意に眼が涙にうるんで来るのを感じた。曽根兵六も、だしぬけに巣を取り上げられたつばめのようだと思った。生死いずれにしろ、兵六には二度と会うことはないだろう。すべてが終わったと思った。末次家を取り巻いていた屋敷を照らしていた日の光、風の匂い、家族との暮らし、粗忽な兵六の思い出、「すべてが終わった」と思う路の胸中には、再び戻らぬ日々への郷愁が静かに湛えられている。
鷦鷯
鷦鷯は登場人物の心のプロセスが見せ場である。新左衛門は貧乏だが誇りが高く、その心根と現実のギャップが面白い。彼は金貸の倅と自分の娘が気安く話しているのに腹を立てていた。しかしその倅が剣の達者であることを知って見直す。頑固者の新左衛門の滑稽な味わいに、思わず笑いが込み上げてきます。短編のなかに不思議なあたたかさを感じます。うかつにも私は藤沢周平という作家を侮っていました。
短編、長編の彼の作品から、藤沢周平は、繊細な日本人の心の機微を伝える日本を代表する誇り高い作家であると心から思います。
結び
藤沢周平の作品を読み始めたのは家事や勤務に多少余裕が持ててからのこと。簡単な短編集だけ覗こうと思い読み始めました。ところがどの小説も見事に私の心を掴み、面白くて夢中になりました。人の心の動きの急所を掴んでいて、何度も読み返しました。全く一字一句、無駄のない表現に魅せられて、気が付けば短編から長編小説へと読み進んでいました。人の心を掴むのみならず、時代風景や食文化など、当時の社会の武士や女性の様子が良くわかります。
中でも短編小説「玄鳥」「鷦鷯」に共通することはやはりこの時代の女性の「つつましさ」です。文章が端正でリズムがあり、読み手に心地よさを与える。特に「鷦鷯」においては思わず笑いが込み上げてくるのは作者の描き方の見事さからだ。何度でも笑ってしまいます。
時代背景が手に取るようにわかり、そして自然描写の見事さ、当時の食文化の明確さ、登場人物の人格、どれをとっても藤沢周平の描く世界は美しく人情の良く伝わる作品だと思います。日本の自然風景を読んでこの国に生まれてよかったと思わせる、美しく、決して嫌味がない素晴らしい表現の仕方。登場人物は、貧乏の中にも気品があり、凛としています。
時代の流れは止めようがないし、人の考えも変わります。けれども現代人は昔の人々から学ぶものがあると思います。それは何か?
「人情」「友情」「品格」「つつましさ」、等といったものではないでしょうか? 昔が全て良しとするものではないですが、藤沢文学を読み私は現代人が忘れていることが多々あることをしみじみと感じました。原点に戻り今一度考えてみる価値のある文学作品であると思います。ただの小説として捉えるのではなく、現代社会を考える材料にするべき素晴らしい作品であると思えてなりません。先人たちがこれまで伝えてきた日本の風習や情緒を、昔の事として処理するのではなく、現代社会を少しでも住みよい社会にする気付きや手立てになるように思います。
このようなことを、この小説を読みながら感じました。日本の社会が、そして世界がもっと優しく、節度ある世になることを願いつつ思いを募らせながらの読書となりました。
合 掌