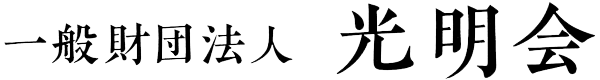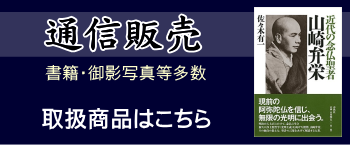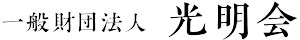乳房のひととせ 上巻
中井常次郎(弁常居士)著
◇聞き書き その七〈つづき〉 大正9年6月1日夜 恒村医院にての話
(二)光明主義の宗趣
念仏三昧を宗となし、往生浄土を体となす。
宗とは法の貴ぶ所、体とは行の帰趣する処。
通じて道に入るには宗趣を明らかにせねばならぬ。浄土の三部経は皆念仏三昧を宗とすべきを説いてある。宗とは信仰の中心点である。これを明らかにせねば、信仰の目的が達し得られぬ。吾々は目でも口でも、手でも如来を念じ仕えねばならぬ。わが真正面に大いなる如来のまします事を信ぜよ。如来の実在とそのみ力とを信ぜよ。吾々の五官は皆使われるものである。その使い手なる精神(自我)が如来に帰命するのである。
宇宙に無量の諸仏が在す。その中心は、我々の自我に相当する阿弥陀如来である。人に二つの精神無き如く、宇宙に唯一独尊の如来在す。その如来と自分との関係即ち神人合一の理法が有る。それを捕えると、あとは従いて来る。身は心に因って自由にされる。心を降参させると、身は従いて来る。心を屈服させぬと、身体は自由にならぬ。宇宙を吾が物にするには、如来を吾が物とせねばならぬ。それには、自分の全体を如来に献げねばならぬ。吾が心を献げる事は、己が全部を献げる事になる。わが心を如来に献ぐれば、如来は吾が物となる。如来に取られるは、如来を取る事になる。そうすると宇宙全体が自分のものとなる。
自然界に太陽が在って、世界の生物を生かす如く、心霊界には如来なる太陽が在って、衆生の心霊を活かし給う。その如来と自分の心とが一つになる事を念仏三昧という。三昧とは一つになる事である。如来が見えても、見えなくとも、如来の実在を信じて、一心に念仏すればよい。
赤子が生れた時、総てが生れたのでは無い。目が見えて来れば、視力が生れたのである。智慧がつけば、智慧が生れたのである。胎内から出れば、身体が生れたのである。その後、色々のものが生れる。生れるという事は続くものである。
光明会員は如来の子としては、まだ赤子である。何も解らぬ。如来が解らぬ。一心に念仏して、信仰が育って来ると、次第に如来が知れて来る。そこで仏子の自覚が生れて来る。
浄土に生れるというも、光明生活するというも同じ事である。名は異なれど実同じ。一心に念仏すれば光明生活となる。何となくその気分がして来る。娑婆にいる間は、心だけ光明中に活かせて頂き、此の肉体が死ねば、仏界の人として生れ更るのである。心は今から浄土に生れておらねばならぬ。
身体が丈夫であるほど食欲が盛んである如く、信仰が進めば、心霊の糧なる念仏の必要を益々感ずるようになる。浄土とは仏智の現れた処であり、娑婆は凡夫の阿頼耶識の所感である。人間界の事は蠅には解らぬ。人間が不浄とするものを、蠅は不浄と感じない。蠅は人間にならぬと、人間の心を知る事ができない。私共の心を仏心に比ぶれば、蠅に等しきものなれば、三昧に入り仏心を知るまでは、仏界を見る事ができない。一心に念仏すれば、次第に仏心が生れて来る。極楽はここに現れて来る。
(三)南無の解釈(救我と、度我)
闇黒、生死の此方から、光明、涅槃の彼方へ到るのが救我である。私共の心は真暗であって、生れぬ先も、死の後も解らぬ凡夫である。太陽の光で先方は見えるけれども、心の目は一寸先も見えぬ。初めは、己が心の盲目である事を知らぬ。自分が心霊の盲目である事に気付けば、少しは信仰心も起るであろう。
救我とは闇の中から、あなたの光明中に入れて頂き度いという事である。度我とはあなたの光明の中に入れて頂いた上、更にあなたの御心の中に入れて頂きたいという事である。人は完全ならば、仏を頼むに及ばぬ。不完全なる生死の凡夫であるから、救い給えと願わざるを得ぬ。初めて信心獲得した時、救われたのである。それより一歩一歩、光明中に入る。即ち救我より度我へと進む。闇より光明への救いは一度であるが、度我は永遠の歩みであって、はてが無い。
極楽に生れるのは、仏となる為である。仏と成るは衆生を救う為である。衆生を度する目的は、凡てと共に永遠に楽しい生活がしたいからである。一人だけ偉くなるとも、真実の楽しみとはならぬ。極楽の楽みは凡ての人が同様に完全でありたい事である。
(四)宗教は如何なる真理を教うるか。
宗教に形式と内容との両面がある。それは理の念仏と事の念仏とである。真理であるが有難くも面白くも無い事を悟るのが理の念仏である。昔から聖人、賢人といわれる人々は、はっきりか、ぼんやりかの差は有るけれども、宇宙に独尊者が有ると認めている。オイケン曰く「宗教は実感である。科学は五官で知るのであるが、宗教的実感はそれよりも確かである」と。
光明主義は実感の上に立っている。他宗から見て、そんな事は有り得ないというとも、気にかけるに及ばぬ。そんな事は無いという者は、知らないのである。ニュートンはラジウムの事をいわなかったが、ラジウムは無かったのでない。知らなかったのである。
〈つづく〉