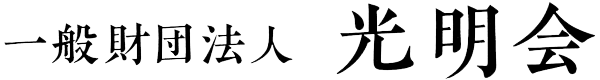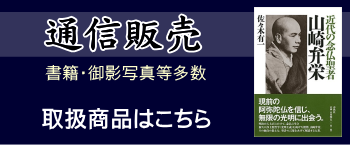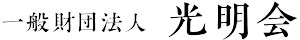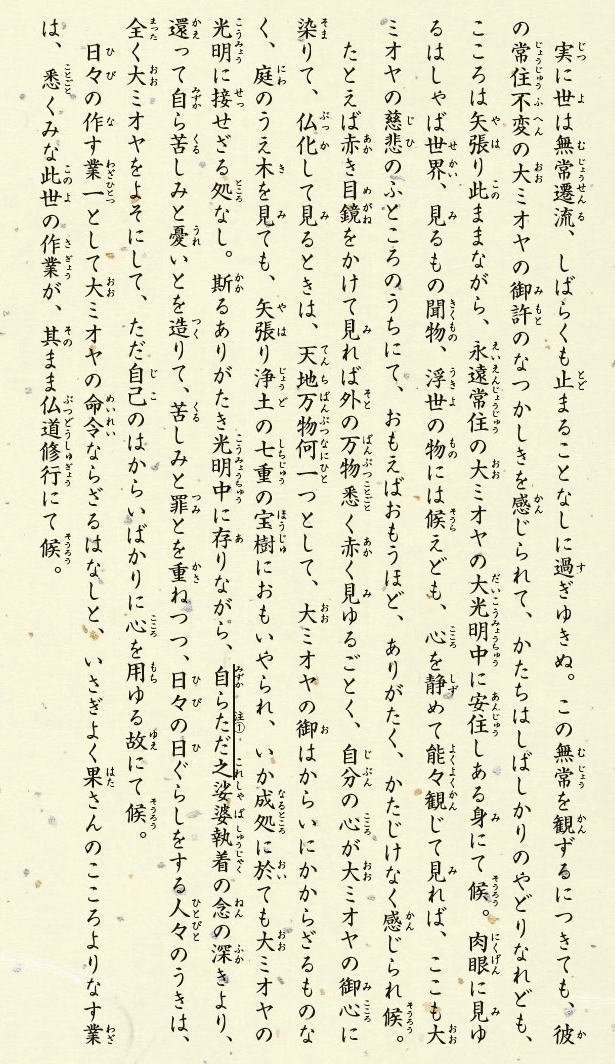
実に世は無常遷流、しばらくも止まることなしに過ぎゆきぬ。この無常を観ずるにつきても、彼の常住不変の大ミオヤの御許のなつかしきを感じられて、かたちはしばしかりのやどりなれども、こころは矢張り此ままながら、永遠常住の大ミオヤの大光明中に安住しある身にて候。肉眼に見ゆるはしゃば世界、見るもの聞物、浮世の物には候えども、心を静めて能々観じて見れば、ここも大ミオヤの慈悲のふところのうちにて、おもえばおもうほど、ありがたく、かたじけなく感じられ候。
たとえば赤き目鏡をかけて見れば外の万物悉く赤く見ゆるごとく、自分の心が大ミオヤの御心に染りて、仏化して見るときは、天地万物何一つとして、大ミオヤの御はからいにかからざるものなく、庭のうえ木を見ても、矢張り浄土の七重の宝樹におもいやられ、いか成処に於ても大ミオヤの光明に接せざる処なし。斯るありがたき光明中に存りながら、自らただ之娑婆執着の念の深きより、還って自ら苦しみと憂いとを造りて、苦しみと罪とを重ねつつ、日々の日ぐらしをする人々のうきは、全く大ミオヤをよそにして、ただ自己のはからいばかりに心を用ゆる故にて候。
日々の作す業一として大ミオヤの命令ならざるはなしと、いさぎよく果さんのこころよりなす業は、悉くみな此世の作業が、其まま仏道修行にて候。
注①―右記二種の出典元では「自分もただ」とあるが原本を確認すると「自らただ之」と読める。
現代語訳
実にこの世は移り変わり、しばらくも止まることなく過ぎていく。この無常を観じていると、永遠に変化することのない、大ミオヤの御許、極楽浄土に心ひかれ〔ます。そして〕この身は、この世にいる間の一時的な仮の住まいではありますが、心はやはり、この世に居ながら、永遠なる大ミオヤの大光明中に安住している身の上なのです。肉眼で見るのは娑婆世界、見るもの聞くもの、儚い世界の物ではありますが、心を静めて〔智慧の眼で〕よくよく観じて見れば、〔来世のみならず〕ここも大ミオヤの慈悲の懐の内、思えば思うほど、ありがたく、もったいなく感じられてきます。 例えば、赤い〔レンズの〕眼鏡をかけて見れば、外の万物は悉く赤く見えるように、自分の心が大ミオヤの御心に染まり、仏心へとお育ていただいて見るときは、天地万物、何一つとして、大ミオヤのお計らいでないものはありません。庭の植木を見ても、やはり極楽浄土にある七重の宝樹と思うことができ、どのような処であっても、大ミオヤの光明に接することができない処はないのです。このような、ありがたき光明中に居ながら、自ら、娑婆世界において執着を深めてしまい、還って苦しみと悩みを造り、苦しみと罪とを重ねつつ、日々〔信仰心なく〕過ごしている人々の苦悩は、大ミオヤを念う心が全くなく、ただ自己の計らいばかりに心を用いるから起こるのです。 日々の務めは、「一として大ミオヤの命令でないものはないと〔思い定め〕、いさぎよく努め果します。」そのような心をもって取り組むこの世の務めは、みな悉く、そのまま仏道修行となるのです。解説
出典
『御慈悲のたより』上巻65~66頁、『ひかり』平成30年11月号8~9頁参照。福岡県島田家宛の書簡。掲載
機関誌ひかり第733号- 編集室より
- 行者(この文を拝読する者)の発熱を促す経典や念仏者の法語をここで紹介していきます。日々、お念仏をお唱えする際に拝読し、信仰の熱を高めて頂けたらと存じます。
- 現代語訳の凡例
- 文体は「です、ます」調に統一し、〔 〕を用いて編者が文字を補いました。直訳ではなくなるべく平易な文になるように心懸けました。
- 付記
- タイトルの「発熱」は、次の善導大師の行状にも由来しています。「善導、堂に入りて則ち合掌胡跪し一心に念仏す。力竭きるに非ざれば休まず。乃ち寒冷に至るも亦た須くして汗を流す。この相状を以って至誠を表す。」