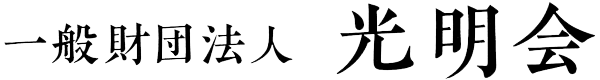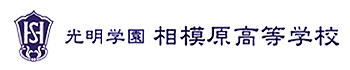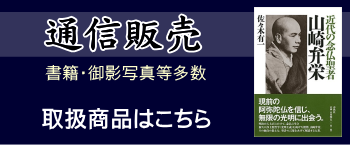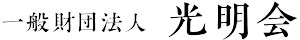山本 サチ子
新河岸川の土手を歩いていると、梅の木のてっぺんにメジロを一羽見つけた。せわしなく枝を渡り歩いている。
隣の木には蝋梅が咲いていて、モズが一羽留まっていた。愛くるしい目をした二羽の小鳥たちは蜜をついばんでいるように見える。淡い日差しの中に小鳥たちは早春の息吹を運んでくれた。
〈虫たちの冬籠り〉
ここ数日の寒さから春はまだ遠いと感じていた。ふと見ると、庭の片隅に遠慮がちに福寿草が咲いている。ここにも春の使者はいたのだ。小さな花から明るい希望を受け取る。植物は正直だ。季節の変化を確実に告げている。しかし、土の中の生き物が地上に出てくる気配はまだない。蟻やキリギリス、他の生き物が地上に出てくるのはもう少し先になるのだろうか。などと地下の生き物に思いを巡らしていたら、幼い頃に出会ったイソップ物語のことが頭に浮かんだ。
小学生時代、学芸会で私達のクラスは「蟻とキリギリス」を演じた。演劇は今、保育園や幼稚園で毎年のように行われているオペレッタとほぼ同じ形式で行われた。
世間では大人向けのオペレッタ「チャルダッシュの女王」などが上演されているものもあるが、やはり私は子供向けのものが好きだ。本来ならば比較すべきものではないかも知れないが、自分の中ではそのように受け止めてしまう。
当時はどこの家も家族が多く、学校行事には多くの家族がお弁当を作り観覧していた。家族の参加は子供達からすると周囲の人々から守られている意識が働き、私自身も心地良い温かさを感じていた。私たちは蟻さんチームとキリギリスさんチームの二つに分かれた。私は蟻さんチームに所属した。キリギリスたちは、夏の間、汗水たらして働く蟻たちを指さして笑う。
毎日こんなに楽しいのに汗水たらして働くなんて馬鹿だなぁ
とキリギリスたちは口々に言う。
夏の間に汗水たらして働いていた蟻たちは、冬の間に食べ物に困ることなく元気に春を迎えるための準備に勤しんでいたのです。
やがて冬になり、夏の間働かず怠けていたキリギリスが、寒さのため、冬ごもりをしていた蟻たちに哀願して助けを求めます。
蟻たちはお腹を空かしたキリギリスたちに食べ物を与え仲良く春を待つというストーリーである。
夏の間に汗水たらして働いていた蟻たちは食べ物に困ることなく元気に春を迎えることが出来たのだった。キリギリスに食べ物を欲しいと哀願された蟻たちは快く承諾したのです。蟻たちは語りながら歌った。
夏の間あんなに遊んだからだわ。今度からは怠けないで働きましょう! さあご馳走を食べて元気を出しなさいよ。
そして「楽しい、楽しいクリスマス」…と音楽に合わせ輪になり皆でてダンスを踊った。
男女共にクラスメートたちはダンスやセリフを入れながら演じきり、大きな喝采を受けました。観客たちの拍手はかなり続き、子供たちを讃えました。みなで頑張ったあの時のオペレッタは今、思い出しても楽しい光景。
小学三年生の幼い頃のあの思い出がこころに深く刻まれている。それは小さいながらもクラスのメンバーの団結力が成功させた。あの時の楽しかった時間が素晴らしい時間であったからこそなのだと思う。何十年も経た今でも鮮明に覚えている。
この演劇を周囲の人たちはとても良かったと口々に評価してくれたこと、そして皆が団結して成功に繋がったことなどが、こどもたちにとっては嬉しかったのだ。
こんなふうに土の中の生き物のことを考えていたらどんどん昔の記憶に辿り着き、小学生時代の学芸会まで記憶は蘇っていったのです。
今の時代ならこのような学校行事で楽しむことなどは昔ほどは盛り上がらないかも知れない。けれどあの時、家族と食べたお弁当のおいしさや友達との会話は忘れられない。単純で幸せな田舎の家族集団の話なのであるけれど、この時感じた幸せがまさか一生繋がっているなんて不思議な気がする。
こんな自分は単純な人間であると人には笑われるかもしれない。けれども周囲の人達のあの時の微笑みや一緒に過ごした時間は歳を経た現在でも自分を幸せな気持ちにしてくれている。あの時クラス担任は、「みんな仲良く力を合わせ団結して楽しいクラスを作っていきましょうね」…との言葉は、素晴らしい導きであったと今改めて思えるのです。昔は田舎と言えども人口が多かった。何処の家庭でも子供が沢山いてとても賑やかだったのです。冬は雪道を三キロ先から学校まで通う子供達もかなりいた。それでも学校を休まず登校拒否は無かった。周囲の人たちの見守りが当然でしたし、いじめも起こらなかった。そういう時代が懐かしくて微笑ましさを感じる。そんな思い出の多い小学校も現在では数校が統合され、子供たちはスクールバスで通学している。
〈結び〉
このような「単純な思い出話」を書いてと苦笑されるかもしれない。しかし私はやさしい行動や言動などが、しあわせに繋がっていると考えている。
話し方においてもそれは言えるのではないか? 難しい話も平易な言葉で伝えることは聞き手の心に響く。率直で解り易い言葉で伝えることが大切だと思っている。
蟻とキリギリスは確かに小学生向けかも知れないが、この話しの裏には「周囲との和」が内在されている。つまり人間で言うならば他者との間の関係性だ。周囲との関わり方によっては増々溝が深まることもある。私自身も周囲との「和」を守り平和に過すことが難しいことがある。
そんな時こそお念仏に助けられるている。「他の人の意見が何が何だか分からない。とにかく私は正しいのだ」などと思い自分の考えを譲れないことがある。そんなとき「私は本当の南無阿弥陀仏を申し生きているのだろうか」…と、自己嫌悪に陥ることがある。けれども最近ではネガティブに考えては少しも進まない。窮地に立たされたときそんな時こそやっぱり「南無阿弥陀仏」を申す他はない。どんなことも「南無阿弥陀仏」に込めて生活すると真実や未来が見えて来る気がする。
「戒」「定」「慧」この三つに対し、どこまで即した生活に近づくことができるのか、凡人の自分には正直とても厳しさがある。しかし日々の生活を改め目覚めた生活をすれば多少なりとも近づくことが出来るのではないかと考え自分を励ましている。
嬉しい時、つらい時、どんな時にも南無阿弥陀仏を称える。日々の生活の中で南無阿弥陀仏を申すことで心の平安を保つことが出来る。この心の法灯を胸にたずさえて、日々の生活をおくることが幸せに繋がっていくと信じている。
み名を呼ぶ声にこころの雲はれて
さやかに見ゆる月のおもかげ
(山崎弁栄上人詠)
合 掌