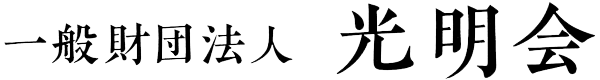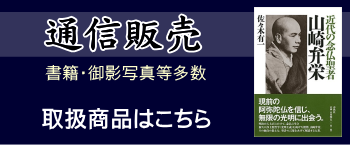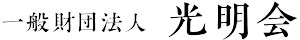石川ゆき絵
ブラジルの田舎にて家族三人で始めたレストラン「ゑん」が五歳を迎えた。とても小さな店なのだが、多くのお客さんが訪れてくださっている。五年間ここで、食堂を営めていることがとてもうれしい。どの料理も胸をはってお客さんに提供できておりこの生業が楽しくてたまらない。しかしたまに本気で「もう飲食店を辞めたい」と思うことがある。
どんなときに辞めたいと思うか!? テーブルから戻ってくるお皿が空っぽじゃない時だ。
ブラジル人はとにかく大量に食べものを残す。残すことに罪悪感のかけらも持たない。その残し方は、人参が嫌いやから皿のすみっこにそうっと残すというようなかわいげのあるものではなく「その注文量は多すぎて食べきれないと思いますよ」と、あらかじめ伝えたとしても強行突破でどっさり注文し、当然のようにいっぱい残すという激しく残虐なやりかたなのだ。
わたしは日本人なので「いただきます」の意が「いのちをいただきます」ということを知っているから、皿のなかに残され捨てられる命たちをみるのが悲しい。「ブラジル人は、わたしたちが生きるために動植物の命をいただくことについて感謝しないのかな? ありがとうって思わんのかな? と、食べ残しがたくさんあるお皿を見てしょんぼりする。
ブラジル人がなぜこんなにたくさん残すのか、想いめぐらせたときに、「命をいただく、っちゅう発想がないからかな!?」と思い至る。ブラジル人の多くはキリスト教徒で、キリスト教では(大雑把にいえば)食べ物は神様から与えられたものという概念だろう。
そんなふうに思っていたので、先日インターネット上で、ブラジル人の子どもたちと一緒に作ったおにぎりを皆で食す前に「いただきます」を教えている日本人が、「神様ありがとう、いただきます」って言ってる動画を観て「なるほど」と思った。そしてがっかりした。「言葉の真意を含めて日本食・日本文化を伝えてほしいなぁ」と感じたのだ。
異国で日本食堂を営むわたしは、文化をも含めて母国・日本の食事を提供する責任があると思っている。なので、わがレストランのしょっぱなからの根底にあるのは「食は命」。食がなければ命も継続できぬのだから食はなくてはならない、肝腎要なものだ。
弁栄聖者の食前・食後の「光明食作法」では、霊の糧をわたしたちに与えてくださるのは阿弥陀如来様だということが解る。いただく命を創造されたのは如来さまであるから、おおもとをつきつめればキリスト教と同じで、如来様・神様から霊の御恵みを享受いただくと解釈できる。
しかしそれを理解した上でもわたしの心はやはり、個々の命をいただくことで我々は生かさせていただいている、というところにある。そう考えると飽食なんかできないし、一食一食に真摯になれるし、そういう心でお客さんたちに料理を提供することに重きを置きたいからだ。この考えかたは信仰をもたない人にも受け入れられやすいのではないかなとも思う。
ところが! お皿の上の料理はすべて動植物の命からできていると思えば、おいそれと食べ物を残すことなんかできないはずと、わたしは見当をつけていたのだが、ここで暮らすようになって、どうやらそうでもないらしいことが判った。
わたしの暮らす集落ではヤギや鶏を飼っている一般家庭も多く、祝い事などことあるごとに動物を絞めてごちそうを作る。子どもたちもそれに馴染んでおり、絞めることも毛をむしることも日常的に手伝っている子が多い。彼らは日本の一般的な子どもたちのように、お肉はスーパーの発泡スチロール皿の上にあるものではなく、たった今まで庭を歩いていた一羽の鶏である事を十二分に解っているのだ。それなのに、子どもたちを含め集落の人々は、食べものを丁寧に食べない。食べ散らかすと表現してもいい惨状が食後のテーブルの上にはある。
わたしはごはんつぶを残すなという食育を受けたので、米粒や野菜のみならず、大雑把にかじっているだけで骨のまわりに大量に残された肉を見ると怒りすら湧いてくる。たったいま殺めていただいた命を食べ残すとは、どういうことかいな! とずいぶんと頭をひねっていたのだが、子どもたちの言葉のなかにその回答があった。
鶏はただの食べものだ。子どもたち曰く「馬はかっこいい」けど「牛は醜い」。醜いから愛でられることもないただの食べもの(ブラジル人は馬を食べる習慣がない)。牛や鶏は神様から与えられた食べものとして存在しているので、命としてカウントしないという発想に近いようなのだ。なので飼い犬が死んだときは号泣するが、鶏を絞めるのはケロっとしている。
やはり食文化は奥が深い。大自然を有するブラジルは、食糧自給率も高く広大な土地に豊潤な農作物が実り畜産動物がいたるところを歩いている。食料に困った歴史があまりない点も、食べものを残す習慣につながっているのかもしれない。
わたしが子どもの時分には大正生まれの祖父母が同居していたから、お米の一粒を重要に受け止めていたけれど、もしかすると今の日本の食卓の様子も、わたしが十四年日本を離れている間にずいぶん変わっているのかもしれない。給食を残さず食べなさいっていうのも教育として行き過ぎだ、虐待だ、という日本の世論も昨今はよく目にするし、今の時代だと万国共通っていうくらい世界の食卓で広がる光景は、携帯電話みながらの食事かな。わがレストランのお客さんの子どもたちも、ずいぶんと小さい子でも、みんなスマホを持っていて食事中も離さない。
ブラジルの食育はわたしには驚異でしかない。「嫌いなものは食べなくて良い」が大前提にあるから野菜を食べない子どもは多い。「うちの子、野菜がお皿に載ってるだけで何も食べなくなるから野菜ぜんぶ別のお皿に入れて焼きそばを出してね」とか「うちの子はオレンジジュースのつぶつぶが嫌いだから丁寧に濾してね」とか厨房に言いに来る母親も多くいて、その度に日本との違いに驚く。
ブラジル人男性と日本人女性の夫婦が子ども連れで訪れたとき、日本人の母親は食べず嫌いをする息子に「食べられるものが増えると楽しいよ。食べてみてごらん」と、うながした。すると父親は彼女に食ってかかった。「なんで無理に食べさせる!? 僕は子どものころ野菜なんてひとつも食べなかったけど大人になった今も何一つ困ることはない。息子が食べたくないものを無理に食べさせようとするな!」と強い剣幕で妻に抗議していた。異文化の融合はたいへん困難なのだなと、じっくり納得させられた一幕だった。
ちなみに食後の祈りの文句はキリスト教にはないようで「ごちそうさまでした」は日本特有の食後の言葉なのだろう。わたしは命をいただくことに手を尽くしてくださった人々への感謝であるこの言葉も大好きだ。お米を育てた農家さん、加工した人たち、販売してくれる人たち、お米を洗って炊いてくれる人、そしてそのお米を料理する人への感謝。
たーーくさんの人々が命をいただくことにたずさわっており、最後にようやくお皿の上に料理ができあがり、それをありがたくいただくことができるというミラクル。ごはんを食べることができるってことは、当たり前じゃないんだなぁと、一心に感謝が生まれる「ごちそうさまでした」。
お客さんが帰り際に厨房をのぞいて「美味しかった。ありがとう」って合掌してくれたときは、料理人の夫もわたしもウエイトレスとして店を手伝っている娘もガッツポーズ。本当にうれしい。そんなお客さんから戻ってくるお皿は舐めたようにぴかぴかなので、ますますうれしくなる。
やっぱ食堂はやめられないなぁと思いながら満面の笑顔でお客さんを見送る。にこにこ笑顔で「如来様ありがとうございます」と合掌する。南無阿弥陀佛